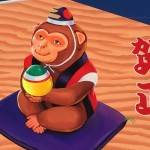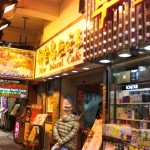電気料金を節約する「電子ブレーカー」とは?

経営改善に向けた重要な施策として、水道光熱費、中でも電気料金の削減があります。電気代は主に共用スペースの使用量にかかってくるので、どうやって節約するのかわからないというのが普通の感覚だと思います。しかし、最近のテクノロジーの進化でとても便利なシステムが開発されています。
電子ブレーカーの商品自体は10年以上前からあったようですが、賃貸マンションに導入されるようになったのは4〜5年ほど前だそうです。しかし、現在でもこの機器に詳しい不動産会社は少ないようですし、必ず電気代の削減につながるわけではなく、物件によって効果の有無がありますので、不動産投資家の間でもまだまだ普及し難い点があるのだと思います。
難しい話は苦手なので、私の把握している範囲で平易な言葉を使って説明させていただくと、ブレーカーというのは、複数の機器で使われる電流の量を感知する装置であり、そもそも過電流による出火を防ぐ役割のものです。電子ブレーカーはその電流をCPUというコンピューターのデジタル制御によってより安全に、過電流を抑える機能を備えています。
そして、電子ブレーカーを導入して電気料金の削減をはかる、ということは、いわゆる携帯電話の料金プラン見直しのようなものだと思います。最初はよくわからなくてとりあえず高いプランに入ったけど、実際に使っている量に応じて最適なプランに加入し直す、というイメージです。
一般家庭で支払う電気料金は、契約種別を「従量電灯B」と言い、照明や家庭用電気機器の使用にかかる料金体系から成っています。契約の単位は「A(アンペア)」で表され、10Aから60Aまで7段階の基本料金と、使用量に応じた電力量料金の合計を支払います。そしてこれは、収益物件でも同じものを契約します。
そしてもう一つ、業務用の電力契約として、工場や商店、マンション等でモーターなどの強力な電動機を使う需要に対応したものがあり、「低圧電力」という契約種別になります。契約の単位はkW(キロワット)で表され、1kWあたりの単価計算による基本料金と、使用量に応じた電力量料金の合計が課されます。なぜ「低圧」というのかというと、これは契約電力が50kw未満の施設用で、さらに大きなものには「高圧」「特別高圧」のカテゴリーがあり、ビル・百貨店・スーパー用です。ここでの説明は、多くのマンションに適用される「低圧電力」契約に限定して話を進めます。
さて、電気の契約に「従量電灯B」と「低圧電力」の2種類があるところまではご理解いただいたと思いますが、電子ブレーカーの導入によって効果が表れるのは、主に「低圧電力」契約の部分です。
「低圧電力契約」には2種類の決め方があり、普通は「負荷設備契約」の設定になっていることがほとんどです。これをもう一つの「主開閉器契約」に変更することにより、基本料金が削減できる、というノウハウです。
それでは、どのくらい削減効果があるのか、私の実体験を踏まえて明日、解説します。
頭金ゼロで7億の資産をつくる
桜木不動産投資塾
のホームページはこちら
関連記事
物件を購入したら、経営改善のためにガス設備をチェック!

物件を取得後の経営改善のために、まず私が最初にチェックする設備は、ガスです。
都市ガスかプロパンガス(LPガス)か、を確認するところからスタートします。
その物件が都市ガスを採用している場合にはプロパンガスへの切替、既にプロパンガスを使用していれば、別のプロパンガス会社への切替を検討します。
都市ガスはこれまで公共料金として提供されていました。そこに一般企業のプロパンガス会社が参入し、いろいろなサービスをつけて顧客獲得をしている、というのが業界の仕組みです。
入居者目線では、まず一般的な印象として、
「都市ガスの方が安い」という定説があります。
だから入居者さんも「ガスは都市ガスに限る」と指定して部屋探しをする人も少なくありません。
それを感じている管理会社も、都市ガスの方が客付けしやすいと思っているセールスさんが少なくありません。
でも、日本企業を舐めてはいけません。単に価格が安いだけの都市ガスに対し、黙って指をくわえて見ているだけのはずがないのです。
2016年からは電力市場の完全自由化が決定しており、更に都市ガスも2017年に全面自由化が予定されていますので、そうなるとますますエネルギー業界全体で熾烈な競争が予測されます。
例えば、ガス設備の中で最も修繕リスクが高いのが給湯器の交換です。大体10年〜15年くらいで交換の時期がやってきます。世帯の大きさによっても異なりますが、その費用は10万円〜15万円程度。これが徐々に部屋数分だけかかってきますので、30室ある場合には300万円〜450万円を将来の修繕費にあて込んでおかなければなりません。
これがプロパンガス会社と契約すると、ガス会社負担にて交換できるサービスが付帯されてきます。プロパンガス会社としては、継続的に顧客を確保することができれば、給湯器を提供することは、それほどハードルが高くないのです。
プロパンガス会社は世の中に2万社以上あると言われ、その中でしのぎを削って顧客獲得しなければならないので、ガス会社さんも切替には積極的です。
また都市ガスは、万が一の災害時には供給が完全にストップしてしまいますが、プロパンガスは単独の設備を敷地内に有しているため、早く回復できる可能性があります。
この他、カラーモニター付きドアホンの設置やエアコンの永年無料交換などのサービス、オーナーへのインセンティブ(報奨金)等もありますが、あまり調子に乗ってあれもこれも要求すると、それは必ず入居者のガス料金に反映され、個々の負担金が上がります。やがてそれが不満となって退去を促す原因にもなりかねないので要注意です。
また、プロパンガス会社ならどこでも良い、というわけではなく、契約条件をしっかりと確認しないといけません。
私がかつて木造アパートを売却した際、新築での購入から2年ほど経っていましたが、管理会社とプロパンガス会社がグループ提携していたため、契約書上、どちらか一方を解除することができない内容になっていました。しかもプロパンガス契約を解除する場合には、残存の設備償却費用を負担しなければならず、それだけで240万円かかるとのことでした。
その木造アパートの買主さんがどうしても管理会社を変えたいと要望されたので、止むを得ずプロパンガスの設備費分、売却価格を下げて売り渡す羽目になりました。
このように、契約解除できない期間が設定されていたり、プロパンの設備に償却期間が設けられていて、解約時には一気にその分を負担しなければならないこともあり得ます。いつまでその物件の所有するつもりなのか、という腹づもりと合わせ、よく検討・吟味した方が良いです。
私が取引しているプロパンガス会社は、都市ガスから切り替える際、値段が高くならないことを条件にしています。そしてそれを入居者さんにきちんと説明してもらいます。
その上で、給湯器交換無料のサービスを付けてもらっていますので、オーナーにとっては交換費用を節約することができ、経営改善が図れます。
更に先般購入した物件では、ファミリータイプにも関わらず追い炊き機能がついていませんでした。これは客付けの際にかなり深刻な阻害要因になります。そこでプロパンガスのセールスさんに相談し、給湯器交換に加え、新規入居者から順次追い炊き機能を設置してもらうようにしました。これで新規募集家賃を5,000円アップし、現入居者さんには賃料2,000円アップを条件に、追い炊き機能追加を提案しました。
こうすることで部屋の価値も上がり、入居者の満足度も上がって、やがて家賃収入も増えます。但し、この進め方にはやはり管理会社とプロパンガス会社の理解と協力があってこそ成果を生み出すものですので、よい会社・信頼できる営業マンと出会い、自分の主旨・目的・希望をきちんと説明した上で推進してください。
頭金ゼロで7億の資産をつくる
桜木不動産投資塾
のホームページはこちら
関連記事
横浜銀行と東日本銀行が統合すると、融資枠はどうなる?

2016年4月を目指して、横浜銀行と東日本銀行が経営統合するそうです。楽待に会員登録している人には、本日「不動産投資新聞」のメールが届いたと思います。そのタイトルが『横浜銀行と東日本銀行の統合は不動産投資市場にどんな影響がある?』というものだったので、興味深く読みました。
リンクはこちら。
●記事の概要
横浜銀行は、横浜市を中心に国内204店舗を持つ大手地方銀行で、不動産の融資に積極的な金融機関としても有名です。一方、東日本銀行は東京を中心に80店舗を構えており、これまで横浜銀行ではカバーしきれていないエリアを管轄しています。
そう考えると、今まで横浜銀行で融資を受けたかったのに、エリアではじかれていた分、今後融資を受けられる可能性があるのでは、と都合良く考えてしまいます。
ところが、その記事の中に書いてある内容では、現役の東日本銀行の行員と元メガバンクの融資課長が声を揃えて「先のことはわからない」とした上で「融資枠」について言及されていました。
「たとえばA銀行、B銀行に融資枠が1億円ずつあったとして、二つの銀行が合併しても、融資枠は2行分(2億円)にはならない。しかし今回は経営統合なので、持ち株会社の傘下に2つの銀行が入ることになるため、融資枠はそれぞれに設定されるだろう。」
●気になるところ
このコメントを読んだ時、私の関心事は「融資枠」というキーワードです。
融資枠とは、何なのでしょう。その人に決められた融資上限の限界のように読み取れます。
よく不動産投資家の間でも、◯◯銀行の融資枠は年収の20倍まで、とかいう言葉を耳にしますが、実際にその人に融資できる金額の上限というものがあったとは、少々驚きです。
私がこれまでお付き合いさせていただいている銀行からは、融資枠よりも物件の評価次第と言われていますし、どんなに低い金額であっても自己資金を入れなければ承認されないケースがたくさんありました。
事実、私は一つの銀行から7億円の融資を受けていますが、既に年収の50倍以上になっています。そして今後も良い物件があったら持ち込んで欲しいと言われていますが、その銀行ではいったい私の融資枠はいくらなんだろうと思ってしまいます。
しかし、現役の行員と元融資課長さんがおっしゃるのですから、「融資枠」があるというのは。その銀行においては確かなことなのでしょう。今まで全く意識したことはありませんでしたが、今後融資枠のある銀行とご縁があった時には、ぜひその「枠の基準」について聞いてみたいと思います。
●これからに向けて
私の経験では、自分の枠を過剰に意識することは、自ら可能性を狭めてしまうことになるため、あまり気にすることはないと思っています。一番重要なのは物件の担保価値と収益性であり、これは融資枠があったとしても変わりないと思います。そして、それを評価する銀行の考え方も時期によって変わるものと認識して、前向きに活動される方が良いのです。
頭金ゼロで7億の資産をつくる
桜木不動産投資塾
のホームページはこちら
関連記事
利回りが低い物件しかない時はどうすればいいの?

昨日のブログでは、最近の不動産市況について言及し、2015年のRCマンションの利回りが8%台になっている、というお話をしました。ほんの数年前、2012年あたりでは10%台が普通に出回っていたので、今はかなり物件価格が高騰している、と実感されている方が多いと思います。
2012〜2013年頃に不動産投資に取り組み、十分な基礎固めをされて今は悠々自適な生活を送っている人がたくさんいます。
そういう方が書かれたノウハウ本も多数出版され、
「根気よく探していれば利回りの高いものが必ずあるし、銀行もたくさん訪問すれば低金利で融資が引けるのだ!」
というご自分の実体験を熱く語る向きの内容を目にすることもあります。
●激変した不動産市場
しかし、たった1〜2年で不動産市場は随分と変わってしまいました。私はちょうどその端境期におり、2012年から本格スタートした物件取得活動では、最初の1棟だけは利回り11%だったものの、それ以降はどんなに一生懸命探しても、RCで10%を越えるまともな物件には出逢えていません。あったとしても全空室に近い状態とか、築45年など、どうやっても融資が付きそうない物件ばかりです。特に私はオーバーローンを原則としていますので、築年数や入居状況は融資金額と融資期間に大きく影響して来ます。
というわけで、どう探しても利回りが低い物件しかない場合、それでも購入したいと思う理由があるのなら、次の対策を頭に入れておいて、前に一歩踏み出す、というのも一つのやり方です。
●返済比率が60%未満であれば、購入に踏み切る。
返済比率というのは、家賃年収に占めるローン返済額の割合です。
例えば家賃年収が1千万円の時、
1億2,000万円の融資を3.5%の金利で35年借りた場合、
年間返済額は595万円になります。
こうすると返済比率が60%未満になり、15%程度の空室が出てもまだ持ち堪えられると思います。
この返済比率を実現するためには、
1.金利が高くても、できるだけ融資期間を長く取れるように交渉する
2.融資期間が延びないなら、できるだけ金利の低い金融機関を探す
3.頭金を入れて融資総額を減らす
のいずれかを選択するしかありません。
③ができれば始めから苦労しないと思うので、
やはり①か②を粘り強く探していくしかないですね。
●なぜ物件を買うのか
今後、利回りが下げ止まるのか、それとも更に下がるのか、誰にもわかりません。
しかし、不動産市場で最も強いのは「物件を持っている人」なのです。いつの時代も土地や建物を持っている人が、売買の優先権を握ります。
今、とりあえずある程度の妥協をしてでも物件を入手し、後から経営改善を進めることはできますが、今、物件を取得しなければ、一向に不動産投資をスタートできない、というのも事実です。机や本にかじりついて評論するだけでいるか、とにかく行動に移すか、その選択によって将来が変わってきます。
●今、やるべきこと
このように、利回りが低いから買えない、と諦めるのではなく、
今こそ金融機関の情報にもっと敏感・貪欲になり、不動産会社やその関連の人脈を丁寧に育てながら、いち早く良い情報をキャッチしていくように努めるべき時期だと思います。
頭金ゼロで7億の資産をつくる
桜木不動産投資塾
のホームページはこちら
関連記事
今、収益不動産の価格相場はどのくらい?

この1〜2年、物件価格が高騰し、利回りが低い物件ばかりで、なかなか購入に踏みきれない方もいらっしゃると思います。
この度、2015年9月に不動産ポータルサイトの健美家に新規登録された区分マンション、一棟アパート、一棟マンションについて、それぞれの物件数、物件価格、表面利回りの集計が公表されました。
リンクはこちら。
概要は以下の通りです。
■区分マンションの平均価格
前月比+3.6%(+50万円)の1,440万円
(前年同月比では+23.6%(+275万円)の上昇)。
表面利回りは8.14%(前月比+0.04ポイント)と僅かに低下し、前年同月比では-1.04ポイント下落。
登録件数は6,740件で減少傾向。
■一棟アパートの平均価格
前月比+0.9%(+51万円)の5,617万円
(前年同月比では+12.4%(+623万円)の上昇)。
表面利回りは前月比-0.05ポイントの9.42%で、僅かな低下に留まっている(前年同月比では-0.67ポイントの下落) 。
登録件数は3,756件で増加傾向。
■一棟マンションの平均価格
前月比-2.8%(-421万円)の1億4,569万円。
前年同月比では+0.7%(+107万円)と微増したものの、2015年の推移からは、2月をピークに「上げ止まり」の様相も感じられる。
表面利回りは前月比-0.04ポイントの 8.52%。前年同月比では-0.3ポイント。依然として低下基調にあるものの、低下幅は縮小する傾向が見られる。
登録件数は2,503件で増加傾向。
ということで、区分マンションも1棟アパートも価格が上昇しています。1棟マンションは、前月比2.8%下がっているとはいえ、利回りはほぼ横ばいか、僅かながら下がっています。
こういうデータはあくまでも平均値であり、必ず全ての物件が同じ傾向にあるわけではないのですが、市場の動きとしては参考になります。
さらに同サイトに後日発表された別の分析結果も見てみます。
●一棟マンション価格は2015年初より645万円下落も利回りはダウン
『2014年4月~6月期から急上昇を続けてきた一棟マンション価格だが、2015年1月~3月期の1億5,458万円を最後にやや下落傾向が見られる。とはいえ、2012年1月~3月期の1億3,130万円に比べると、今期は1億4,813万円と、1.12倍以上。
当然、登録物件投資利回りも2012年10月~12月期の10.20%を最後に10%を割り込み、さらに2014年4月~6月期の9.10%を最後に9%を割り込んでいる状態。現在は8.57%となっており、全国の区分マンションの8.21%よりも高いものの、一棟アパートより低い状態になっている。
ここ1年間の急上昇は特異だったように思われるが、かつて2008年から2009年にかけて1億6,000万円台を超す時期があったことを考えると油断は禁物だ。』
なるほどー。3ヶ月(四半期)ごとにみると、平均価格は1億4,813万円で、
2015年の始めからは徐々に価格が下がっている傾向
と見て取れますが、
3年前から比べると12%も価格が上がっている、
というわけですね。
また、利回りだけにフォーカスすると、
2012年 10%台
2014年 9%台
2015年 8%台
と、じわじわと、しかし確実に下がってきています。
売却価格が上がり、利回りが下がっている、ということは、
家賃相場はそのまま横ばいの状況、ということを意味しています。
更に健美家の分析では、かつて1億6,000万円台を越していたこともあったので、
このまま家賃相場が上がらず、仮にまた物件価格が高騰するような場合には、
まだまだ利回りが下がり続ける可能性もある、
ということですね。
利回りが上がらないならば、私たち投資家は借り入れ金利の低い金融機関を選ぶか、自己資金を増やして返済額を減らすという、厳しいビジネスモデルを選択しなければならなくなります。利回り8%台でオーバーローンを引くなら、金利は1%台が欲しいところです。
そして購入した後も、金利下げやコスト削減などの経営改善に取り組み続けることが一層重要な課題になっていきます。
頭金ゼロで7億の資産をつくる
桜木不動産投資塾
のホームページはこちら
関連記事
融資金額が希望に届きませんでした

今日は残念なお知らせをいただきました。
この1ヶ月、検証に検証を重ね、銀行に融資を打診していた物件があったのですが、本日、不動産仲介会社の方からお電話をいただき、
「残念ながら今回は希望の金額に届きませんでした」
とのことです。
本腰入れて不動産投資を初めて3年、幾度となくローンを申し込み、幾度となく断られて来ました。もっと簡単に言うと、これまでに融資承認が下りたのは5回だけです。
そのうち2回は売主さんの都合で他の人に売られてしまったので、実質うまくいったのは人生で3度だけ、ということになります。
ではなぜこんなに苦労しているのか、赤裸々にお話してみましょう。
難しい融資の典型的な例とも言えます。
1.すべてオーバーローンをモットーにしている。
オーバーローンとは、物件価格に諸費用を合計した、取得にかかる費用をすべて融資で賄うものです。私はこれまでの物件はすべてオーバーローンで購入してきました。つまり自己資金を一切出すことなく、賃貸経営をしています。
本来なら物件価格の2割程度の自己資金が必要と言われるところを、何とかして手持ちを出さずに利益を想像しています。
だから毎回、融資の希望金額が大きくなり、なかなか承認されないのです。
2.積算が思ったよりも低かった
積算とは、物件の価値を図るための指標で、銀行が融資をする金額を算出する際の評価基準になります。
積算についてもう少し詳しい説明はこちら。
今回の銀行は、属性よりも物件の評価を重んじる金融機関だったので、その評価が高ければ、売買価格にあまり関係なく、見合った額の融資を出してもらえそうでした。
ただ、必ずしも積算だけが指標ではないので、収益での評価などさまざまな判定を経て、銀行独自の評価が出ます。それが今回は売買価格にも満たなかったので、オーバーローンは到底無理、ということになりました。
●失ったもの、得たもの、そしてやるべきこと。
物件価格は3.8億円で、利回り7.8%でしたので、満室時の年間キャッシュフローは760万円。
つまり、約700万円の年収が水の泡になって消えた、ということです。
こう考えると、「逃がした魚はデカい」と悔やしさで一杯になりそうですが、それが不動産投資の世界。言ってみればこんなことは日常茶飯事です。
それでも、この物件情報をくれた不動産仲介会社の方に心から感謝します。私の今の状況・資産背景等を鑑みて、融資してくれる可能性が最も高い銀行にあたってくれました。
その結果がNGなのですから、きっとこの物件は買わない方が良かったのだろう、と思うことにしています。
逆に、評価が高い物件さえあれば、すぐにでも融資してもらえることがわかったので、
その点では一歩前に進みました。
そして、残念がっているヒマはなく、すぐ次の物件を探し、紹介してもらえるよう、御礼のメールと次へのお願いをしていくのです。
頭金ゼロで7億の資産をつくる
桜木不動産投資塾
のホームページはこちら
関連記事
Airbnb って何ですか?

最近日本で注目されている空室対策として、Airbnb(エア−・ビー・アンド・ビー)が注目されています。やはり不動産賃貸業は、リフォームして、部屋を貸す、という単純なビジネスモデルになっているため、ちょっとでも刺激のありあそうな話題があると、すぐに飛びつく傾向にあるのかもしれません。
Airbnb は、Airbed and breakfast と言って、英語圏でいう小規模宿泊施設の意だそうですが、要するに、寝るところと食べるものが提供される部屋のことなんですね。
自分の部屋をAirbnbに登録しておくと、やがて宿泊を希望する人がいれば連絡があり、細かい条件を確認し合って、宿泊を請け負う、という仕組みです。
Airbnb の会社は、2008年にサンフランシスコで発足されました。現在Airbnb.comサイトに登録されている物件数は世界で80万件以上、サイト利用者つまり宿泊客数は今年だけで2,000万人を越え、年間総取り扱い額は600億円を猶に越えるそうです。
マンション・アパート経営の中で、そういった需要が多様化・拡大していく可能性にいち早く目をつけたオーナーが、次々と成果を収めていく様子が取り上げられると、つい自分も同じようにしてみようかな、と思うのも無理ありません。
確かに、月の賃料が5万円の部屋がなかなか埋まらなかったとして、Airbnbを経由して短期に貸し出すことができた場合、例えば1泊5,000円とすれば、10日で一ヶ月分の家賃を回収できることになります。
しかしながら、Airbnbならではの懸念点もあるようですので、安易に手を出す前に、よく調査されることをお勧めします。ちなみに私の懸念点は以下の通りです。
1.部屋に宿泊用の設備を導入しなければならない。
少なくともベッドは必須です。その他、冷蔵庫やテレビなど、本来ホテルに標準装備されているものをベースに、必要な設備を検証するところから始まります。当然その分のコストと管理費用がかかってくることになります。
2.利用者の入れ替え時にはどんな手間が?
ホテルではないので、退去時にベッドメークや掃除など、次の人が違和感無く利用できるためのケアが必要になってきます。もしも汚されたり傷つけられたりしたらどのように保証されるのか、調べて対策しておく必要があります。
3.セキュリティーは大丈夫か
Airbnbは基本的に一般人同士が任意にやりとりするシステムですので、万が一事件が起こった場合、その補償はどうなっていくのでしょうか。火災などが発生することもないとは限りません。外国人も多く利用するようなので、言葉の壁もあり、残念ながら一人で全部はやりきれないと思われます。
4.旅館業法に違反しているっていう話も聞いたけど?
旅館業法とは「宿泊料をもらって人を宿泊させる営業行為を行うもの」には認可が必要、というものです。しかし、「営業行為」が何を意味するか、不定期での有料貸出しは商売になるのか、という点もグレーで、このままの状態がしばらく続きそうですね。
5.利用者は主に観光客。自分の所有物件はニーズに合致しているのか。
いくら空室対策になるといっても、登録すればすぐにお客さんが入ってくれるものでもないでしょうし、また、利用される日がいつ来るのかわかりません。そのために部屋をまるまる空けておくのが果たして良いのかどうか、読みが必要です。
著名な駅の近くか、観光名所の近くでも無い限り、安易な選択は禁物です。
以上、表面的な部分もありますが、わかる範囲で分析してみました。いろいろ調べていくと、これは、ホームステイのホストのように自分の家の部屋を貸して食事を出したり、旅館業者の新しい集客システムとして機能させるのが本旨なのではないか、と感じています。
マンションの空室対策としてAirbnbを使うのは、たとえ東京オリンピックで宿泊需要が増加するとはいえ、所有物件の向き・不向きをよく検討されることをお奨めします。
頭金ゼロで7億の資産をつくる
桜木不動産投資塾
のホームページはこちら
関連記事
マンションを購入しませんかっていう電話がかかってくるのですが?

番号をどこで調べたのかわからないけれど、「マンションを買って節税をしましょう」という電話がかかってくることがあります。
それは、ワンルームマンションが、一般のサラリーマンにとって最も買いやすく、営業のターゲットになりやすいからです。
価格も800万円〜2,000万円程度で、見ようによってはお手頃価格に映ります。そして1室であることがあたかも自分の家を買うようなつもりで「住宅ローン」のイメージができるからかもしれません。金融機関も新築であれば比較的融資しやすく、自己資金が無くてもローンだけで買えてしまうケースが多いのも事実です。
●ワンルームマンションは買いやすい
実際には、その人の資金背景や投資方針によって異なるため一概には言えないのですが、一般的にワンルームマンション購入(「区分所有」といいます)は、
「気軽に始められますよ」という調子の良いセールストークが作りやすく、手持ち資金が少ない初心者の方が手を出してしまいがちな、危険がいっぱいの案件です。
その理由を少なくとも4つ、挙げておきます。
1. 売却時にはグッと値段が安くなることがほとんど
新築マンションの売買価格には、販売時の莫大な広告宣伝費が上乗せされているため、人が住んでしまった瞬間に、物件本来の価値は、購入時点の価格よりも大幅に下がります。つまり、その物件を持ち続ける間、買った時以上の価値になる可能性が極めて低い、と言えます。
これは、売却を考える時に買った時よりも安くなってしまうことが多く、ローン残債が多いと、売却しても完済できない状況に陥ることがあり得ます。
2. 空室になったら青ざめるしかない
1室しか持っていないマンションが空いてしまうと、次に新しい入居者が入るまで、当然ながら収入はゼロになります。更に物件購入のためにローンを借りていたりすると、その支払いは全額自己負担になります。
東京23区内など需要が圧倒的に多いエリアの物件を買えば、空室がなかなか埋まらないというリスクは少しでも回避できますが、絶対ではありません。
3. 出費はローン返済だけではない
通常、管理費や維持費は入居者の有無に関わらずオーナーが負担しなければならないケースが多くあります。そうなると、単にローン返済を入居者の家賃で賄えばそれで済む、というわけにはいかないので、購入時には収支のシミュレーションを正確に行っておく必要があります。
実際、このことをよく理解せずに投資用マンションを買ってしまい、結局支払いきれなくて、損を出してでも売却せざるを得なかったという人がたくさんいるようです。
4. 節税対策になるというカラクリ
「給与収入から支払った所得税が還付されますよ」という甘いセールストークを聞きますが、マンション1室の収入から必要経費としてマイナス扱いになるのは、不動産取得税と減価償却費のインパクトが大きい最初の1、2年だけ。3年目以降は恐らく収入が増える分、きっちり税金を支払うことになるでしょう。
この4点の結果として、買う時にはセールスマンの奨めに乗って契約したものの、思うように収益が上がらないということでマイナス収支のまま売却せざるを得なくなる、という事態に陥ることが最も多いのがワンルームマンションです。
従ってワンルームマンション投資は、銀行からの融資を受けずに現金で買える人に向いています。ローン返済の額が少なければ、前述のような空室リスクにも大きく悩まされることなく、メンタル的にも折れずに維持できると思います。
●せめて前向きに考えるなら
但し、マンション投資に対する前向きな考え方としては、例え空室になって自己資金でローン返済をすることになっても、それは赤字ということではなく、財産形成のための積立て、と考えることもできます。
通常の銀行預金をするよりははるかにリターンも多く、将来的には自分の資産となるので、ローン返済が家計を圧迫しない程度なら、メリットはあるかもしれません。くれぐれも借金をしすぎないことが前提です。
更に私の考えでは、マンションを買うお金があるならばそれを自己資金として、もっと大きな1棟ものを買う方が、ずっと収益を拡大できると思うのです。
頭金ゼロで7億の資産をつくる
桜木不動産投資塾
のホームページはこちら
関連記事
不動産投資は、誰にも知られずにできるのか?

サラリーマンにとって、副業を職場に知られずにできるかどうかは重要な関心事ですね。
しかし現実には、不動産投資をしているサラリーマンは全国に山ほどいます。
私がかつて所属していた不動産投資塾でも、80%以上がサラリーマンでした。
普通の会社員をしながら、その給料では自分の望む生活ができない、だからといってもう一つ別の職場を持つことなど到底できない。だからこそ、効率よく収入が得られ、比較的リスクが低いと言われている不動産投資の門を叩く人が多いのだと思います。
かくいう私もその一人です。
職場に勤務しながら、別に悪いことをしているわけでもないのに、もしも知られたらいろいろと面倒なことになりかねない、と思うのは自然な心理だと思います。
●家族にも気づかれずに?
「誰にも知られずに」というのが自分以外の人すべて、となると、ちょっと難しいかもしれません。また私の場合、妻が最大の味方になってくれていますので、妻に知られずに不動産事業をすることは考えられませんでした。
同居の家族がいる場合、細かい話ですが郵便物が届くので、全く気づかれないということは難しいと思います。そもそも家族に秘密にしてまで不動産投資をやる意味があるのか、というところから疑問ですが、もしもそうしなければならない事情を抱えている人は、保証人を必要としない融資を模索することになり、郵便物の送り先を自宅以外に設定するなどの配慮が必要になってきます。
●職場ではそれほど心配ない
別居の親兄弟や職場については、話す必要がなければそのままできます。
一番気になるのは「職場」だと思います。副業という名で禁止されているためにNGだと思われる方が多いようですが、実は不動産所得は遺産相続などで普通にあり得る副収入ですので、社会的におかしなことではありません。
あまり積極的にやっているように受け止められると「副業」と見られてしまうかもしれませんが、あくまでも「偶然に得た副収入源」と位置づけていれば、会社として禁止することはできないと思います。少なくとも自分から言う必要はありません。
勤務先の労働規約か勤務規定に「不動産で収入を得ることを禁止する」という文言さえなければ、まず大丈夫なのではないでしょうか。
●住民税額は経理部門に通知される
唯一のチェックポイントとしては、社員の確定申告の内容を細かくチェックするかどうか、という点です。会社としては、社員に給料を支払う際に源泉徴収を行い、年末に誤差を調整するという作業が行われます。
そこから更に、給与以外の所得がある人は、翌年の3月15日までに確定申告をしなければなりません。
そこで所得額が変更され、それに伴う所得税が変更になります。ここまでは自分で作業する範疇なので問題ないのですが、税務署から勤務先へ、所得額の変更が通知され、それに伴う「住民税」の変更も伝えられます。
住民税は、前年の所得額に基づいて、毎月均等支払いが原則ですので、勤務先の給与から天引きされます。従って、前年の給与が変われば当然「住民税額」も変わり、給与の支払い者に通知されます。
但し、その増減の内容が不動産所得かどうか、という細かいところまでは知らされませんので、そこを経理部に追求されるかどうか、が確認ポイントです。
副収入というのは、比較的たくさんの人が何かしらの事情で得ているケースも多く、その内容まで調査するからには、よほど社則で固く禁じられている場合だと思われます。
●事業家には仲間が必要
別の観点で、不動産事業は仲間がいた方が良いです。
いろいろな情報や体験を分かち合うことで、必ず自分の進め方の参考になります。そして時には助け合ったり、ともに遊んだりしながら情報交換をすることがとても有益な業界です。
この辺りが会社組織とは大きく異なる点で、不動産投資家は個人事業主の方が多いためか、新しい人脈を拓くことに積極的です。
必然的にいろいろなことを覚え、自分のビジネス拡大につながっていきますので、ぜひ一人で閉じこもらずに、オープンに活動されることをお勧めします。
頭金ゼロで7億の資産をつくる
桜木不動産投資塾
のホームページはこちら
関連記事
賃貸仲介会社の営業マンをその気にさせる施策とは?
2015/10/05
リアルな活動報告, 最新情報

空室を埋めるために最も重要なカギを握るのが、賃貸仲介会社の営業マンです。
そして私の物件のうちの1つ、ファミリータイプ15室のうちの1室が
もうすぐ退去を迎えるので、速攻で満室にするためには
どうすればよいかを考えています。
一般的に、客付けをしやすくするための施策として
1.家賃を下げる
2.フリーレント(家賃無料の期間)をつける
3.初期費用(保証料、火災保険料、鍵交換費用など)をオーナー負担とする
というのが管理会社から提案されます。
この中で一番わかりやすい施策が「家賃を下げる」ことで、
セールスが最もトークに使いやすい手段です。
しかし、値下げということは、その近隣の家賃相場までも下げてしまうし、
部屋の価値そのものを下げることになります。
従って入居者にとってその部屋に対する思い入れも少なく、
気分が変わった時に容易に退去する可能性も高くなります。
何より、例えば家賃を5,000円下げるということは、
一年間で6万円、二年間で12万円の収入源となり、
ファミリータイプの場合は長期入居のケースが多いので、
年々6万円ずつ収入が減っていく計算になります。
また、管理会社にとっても、管理料は家賃収入の何%という計算になるので
分母となる家賃収入はできるだけ下げない方が、
長い目で見てよい筈なのです。
ですので、どういう施策を打つべきか、管理会社とよく話し合わなければなりません。
競合物件や時期により、とるべき施策は変わってきます。
今回私は、その管理会社を訪問した際、率直に
「どうすれば営業マンの方々が私の物件を積極的に勧めてくれるようになりますか?」
と聞いてみました。
すると、とても言い難そうな雰囲気ではありましたが、こちらが
「何でも言って欲しい」と迫ると、
「一番効くのは、成約報酬を上げていただくことです」
と話してくれました。
「成約報酬」とは、業界ではいわゆる広告費もしくはADと呼ばれているものです。
通常、そのエリアの広告費(AD)は家賃の1ヶ月分が相場で、既に私の物件は1.5ヶ月分を約束していました。それでも、今回はできるだけ短い期間で成約してもらいたいという私の強い思いもあり、思い切って”2ヶ月分”とすることにしました。
その部屋の家賃は106,000円なので、成約すると212,000円を管理会社に支払わなければならないのですが、空室が2ヶ月、3ヶ月と続けば同じことですので、一日も早く埋めてもらうよう、今回は管理会社の要望に沿った形で施策を決めました。
これがこの後どうなるか、どんな効果があったのか、それとも無かったのか、
また報告したいと思います。
頭金ゼロで7億の資産をつくる
桜木不動産投資塾
のホームページはこちら
関連記事
一日も早く空室を埋めるための対策とは?

自己資金ゼロから総資産7億円を築いたサラリーマン大家
桜木大洋です。
今日は私の物件のうちの1つ、ファミリータイプ15室のうち
もうすぐ退去を迎える部屋が1部屋あるので、
空室を埋める対策を打合せするため、仲介業を兼ねているその物件の管理会社を訪問しました。
●過去の苦い経験
その物件は、約2年前にも1部屋空いたことがありましたが、
その時は7ヶ月間も空室が続き、年間約80万円の家賃収入を失いました。
地域的にも家賃的にも決して見劣りする物件ではないのに、
どうしてこんなに空室が空いてしまったのか、
と原因を探っても、
もはやその管理会社の営業マンの優先順位が低かったから
と思わざるを得ません。
今回は同じ失敗をしないように、
まだ退去する前に、客付け会社の担当者を対策を協議することにしました。
●打合せのポイント
空室後の動きとしては、退去後、すぐにリフォームして現状回復しなければなりません。
現状回復するまでの段取りとしては、次のようになります。
①退去日に、入居者立会いのもと、
現状回復の箇所と入居者負担分を決めます。
②その後で内装業者に見積を依頼し、
修繕箇所の提案があります。
③そうしてオーナーである私が
その修繕箇所と見積金額が妥当であると判断し、
発注をかけます。
④リフォーム業者が工事のスケジュールと
材料(壁紙など)手配をします。
⑤実際のリフォームに取りかかります。
しかし、ここまでの段取りを普通に進行させていたのでは、
すぐに数週間が経ってしまうし、今月は3連休もあるので、
平日発注しかできない業者がほとんどですから、
タイミングがずれるとまたそこから3日分、
進行が遅くなる恐れがあります。
ですので私は、
担当の方が立ち会ってもらうなら、
その方の判断に全て任せるので
その場で全て発注してください。
と依頼しました。
後で私に判断されても、素人の私が判断するには
複数の業者の見積を比較し、それぞれの内容を確認していかなければなりません。
それで多少のコストは抑えられるかもしれませんが、
圧倒的に時間のロスになります。
それよりも
「客付けに最低限必要なレベルをプロの目で判断してください」
と判断基準を明確に伝え、その担当者に一任しました。
これは管理会社の方を信用していないとできませんが、
逆に「そこまで任せてもらえるなら」、
とモチベーション高く取り組んでもらうことを
期待してのアクションです。
●内見がすべてのカギを握る
部屋を埋めるには、とにかく内見(入居検討者を部屋に案内すること)を一日も早く実現するしかありません。修繕前の部屋を見せることもできますが、前の住人が住んでボロボロになった部屋を見せても、あまり魅力的には映らないのが普通です。
その状態で成約に漕ぎ着けるには、よほど上手なセールストークが必要になりますが、今回のケースではそれも期待できません。
ですので、まずは退去日の前に、退去後の現状回復のスケジュールをしっかりと打合せし、できる限り早くキレイな部屋にして内見者を案内できる状態にすることが、最善の策なのです。
このようにしても、
実際に現場で修繕箇所を確認してからでないと、
見積→発注→工事完了のスケジュールは明確にできません。
これからしばらくの間、気を抜かずに進捗状況を確認していかなければ、
と思っています。
頭金ゼロで7億の資産をつくる
桜木不動産投資塾
のホームページはこちら
関連記事
不動産収入は不労所得ってホント?

不動産投資を勧める誘い文句に
「サラリーマンのあなたも不労所得を手に入れて、自由な時間を過ごしませんか?」
というようなキャッチコピーを見かけますが、
私の実感としてはいささか違和感があります。
●投資という言葉の意味
自分のお金を何かに預けて、それを殖やしてもっと大きなお金を手に入れることを「投資」といいますが、その投資対象が土地やマンションなどの不動産である場合、それを「不動産投資」と呼びます。
何とまあ回りくどい言い方をしてみましたが、不動産投資は他の投資とは大きな違いがありますので、あえてこういう表現から始めます。
●物件を購入する醍醐味
例えば自分のお金が100万円あって、それで株や債権を買うと、その時の価値は100万円ですよね。でも不動産の場合、100万円持っている人が現金で100万円の物件を購入することはほとんどありません。100万円持っていても、1,000万円の物件を買えたり、もっと高額な物件を購入することができます。
極論すると、1円も持っていなくても、何千万円もの物件を購入できるケースもたくさんあります。
それはなぜか。
そう、銀行(正しくは金融機関)がお金を貸してくれるからです。
なぜ、銀行は不動産を買う人にお金を貸してくれるのでしょうか。
それは、物件自体が「担保」になるからです。
つまり、もしもその人がお金を返せなくなった場合、担保になっている土地と建物を取り上げて売却すれば、大体貸した分の金額くらいは回収できるから、
と踏んでいるからです。
●銀行の考え方
そしてもう一つ、不動産投資で特徴的なことは、所有している間、空室が出ないように工夫したり、建物をキレイに保って物件の価値が下がらないようにする努力が必要になります。
つまり、不動産投資は「投資」というより「事業」なのです。
銀行も、投資をする人になどお金を貸してくれる筈もなく、不動産経営をする人に、事業資金としてお金を貸してくれるのです。
銀行の目線からは、普通にお店を出して商売する人にお金を貸す場合、万が一その事業が失敗したら資金がゼロになって返してもらえなくなるリスクがあるけれど、不動産賃貸業の場合は、まず倒産することはないし、いざという時には担保があるからよほど安全だ、という考え方を持った銀行員も存在します。(私を担当してくれている地銀の支店長の言葉です)
●不動産事業の本質
ですので、不動産で「月収」を得ようとする人は、単に銀行からお金を貸してもらえば自動的に増えていくなどという「投資の概念」は捨て、基本的に「賃貸業を営む」という覚悟を持って臨むことをお奨めします。
「安く買って高く売る」という投資スタイルをお望みの方は、まさに本当の「投資家」となるべくたくさんの資金を用意された方が良いと思いますし、その場合には「月収」という考えは当てはまりません。
不動産経営とは、入居者というお客さんがいて、仲介業者、管理会社、設備業者、保険会社など、たくさんのビジネスパートナーとともに運営するれっきとした事業なのです。
だから私は、自分の活動を「不動産投資」ではなく、「不動産賃貸業」もしくは「不動産経営」と呼ぶようにしています。(タイトルは「不動産投資」の方がキャッチーなので使うことがありますが)
この観点から、不動産賃貸業は、やり方を間違えなければ着実に儲かるし、金融機関をうまく活用していけば成長させることもできます。
不労所得、ということを「働かずに得られる収入」と解釈するなら、それは預金や株、権利収入のことを示すのだと思います。
不動産事業はそこまで楽チンではありませんが、他の事業のようにがむしゃらにならなくても、僅かな勉強とツボを押さえたアクションで、ゆとりある時間と収入が得られるということは実感できます。
頭金ゼロで7億の資産をつくる
桜木不動産投資塾
のホームページはこちら
関連記事
「不動産投資」という言葉だけで、だまされるかもしれないと思っている人が意外に多い

不動産投資に興味を持ち、書籍を読んだりセミナーに参加して、ずっと真面目に勉強してきて、ついにお宝物件を目の前にした時、例えば友人や家族に相談すると
「だまされているんじゃないの?」
と言われた
という話を耳にすることがあります。
その気持ちは少しわかります。
不動産業者っていう言葉だけで怪しさを覚える人も世の中にはいるんだなぁ、と思います。
不動産業というのは、比較的参入障壁が低い、つまり特別な権利や設備がないとできないわけではない業種です。
もちろん簡単ではありませんし、資格や認可、資金も必要です。
その資格は「宅地建物取引士」といいますが、実は不動産業に従事する人全員が持っているわけではなく、各事務所に宅建取引士が1人いれば、あと4人までは資格がなくても良いのです。
そして不動産仲介業は、何億円もの物件を仲介した時に、あっという間に数百万円単位で紹介料が入るので、1回の成約が取れれば非常に効率の良い営業活動になります。売れれば大もうけ。でも売れなければゼロ。そして本人のやる気・やり方次第で成果が大きく左右されます。
ですので、どんな人でも比較的容易に始められ、収入も大きいとなると、危ない筋の人達が関わってく可能性もあるし、頑張ったけど倒産してしまう会社もあります。
というわけで、不動産会社の人が絶対に信頼できるのかと言われれば、保証はできません。しかしTVドラマとは異なり、実際にそういうケースはとても稀なのではないか、と思うのが実感です。
私には多くの不動産投資家仲間がいますが、悪い噂はすぐに流れるか、仲間内でシェアされるかと思いきや、これまで一度も「騙された」という情報は聞いたことがありません。
「だます」というのは、例えばこの物件を売る、と言って
実は売らないか、
もしくはその物件が実在しなかった、
ということですよね。冷静に考えると、これはかなりあり得ないと思います。
売買契約書を交わす時には通常、実際の物件を現場で確認し、金融機関の評価も得て、登記簿謄本を照合して押印するのですから、契約書と現物がマッチしないという可能性はかなり低くなります。
あとは、騙されたわけではないけれど
よく説明を聞いていなくて話が違った、
ということは時々あります。こういう場合は聞く側にも責任があることがほとんどです。
思いのほか修繕費がかかったり、
現場を観に行ったら環境が良くなかったり、
予定していた収益が得られないことは
普通に起こり得ます。
それは騙されたというのとは違い、自身の調査不足・認識不足が原因です。
そういうことが起こらないように、念のため、契約書の内容を確認する必要はあります。
ではどうやって、誰に確認すればいいの?
という状況の方もいらっしゃるでしょう。
そんな時には、まず
自分の言葉で疑問を書き出して、
それが契約書にどういう表現で記載されているか
を目視できるようにしましょう。
「もしもローンが通らなかったら契約解除できるのか」
「一度支払った手付金は戻ってくるのか」
「引渡し後、万が一建物の不具合(瑕疵といいます)が起きたとき、誰が修繕費を負担するのか」
を、仲介不動産業者の人に確認するしかありません。
もしくは顧問税理士がいる場合には
その程度のことは無料でやってくれる可能性があります。
それでも不安な場合には、お金を払って弁護士に聞くしかないと思います。
私は仲介不動産業者の方に確認してクリアしました。
でも、その場合には
「大丈夫ですよ」
という回答ではなく
どこのどういう文言でそれが書かれているのか
というレベルで納得するまで聞きます。
相手の手を煩わせることに気兼ねしている場合ではありません。
仲介手数料もその中に含まれていると思うのです。
知らないことがあっても臆せず、
「知る権利」を持っているのですから、
わかるまで聞くことに迷ってはいけません。
そうしたことの積み重ねの中で、
きちんとした基礎知識を備えていくと、
結果的には上質な人脈が構築されていくことになるのです。
頭金ゼロで7億の資産をつくる
桜木不動産投資塾
のホームページはこちら
関連記事
収益不動産は家のローンや借金があっても買えますか?

不動産投資に興味があるけれど、家のローンがあるのでお金を借りられないんじゃないか
と思い込んでいる人を時々見かけますが、全く関係ありません。
実際、私にはまだ3,000万円以上の住宅ローンが残っていますが、不動産事業への融資としてはそれに関係なく、たった一つの銀行からオーバーローンで合計7億円の融資を受けています。そしてまだまだ買い続けます。
不動産投資を志す方で、金融機関に融資を申し込む時、住宅ローンがあると不利になると思われるケースがあるようですが、これも全く違います。
私はもう何十回も収益不動産の融資を申し込んでおり、一度もそのことでつまずいたことはありません。
逆に、
「既に住宅ローンを借りている人は、
この先、自宅を買うという銀行にとって
突発的なリスクが一つ減っているようなもので、
一つの安心材料になる」
と言われたことすらあるくらいです。
更にまだ収益不動産ビジネスを知らない頃、私は
住宅ローンを繰上返済する
ことが、家計を安定させる上で
誰もが当り前のように行うべきこと
であるかのように考えていました。
ローンは少しでも早く返済するべき
だと思っていたのです。
しかし今では、
住宅ローンを繰上返済して
新たに他のローンを借りるくらいなら、
低金利の住宅ローンをできるだけ長く
借り続けた方が得だ、
ということに気づきました。
収益不動産の融資と比べても、大抵、住宅ローンの方が金利は低いはずです。
低金利のローンは、出来るだけ長く借りておいた方が良いと私は思います。
一方、
金利の高いノンバンクのローンを借りている場合には、
できるだけ早く返済した方が良いです。
金融機関は現在の負債額を見るときに
「担保があるかどうか」をとても重要視します。
ですので、無担保で贅沢な買い物をしていたり、形の残らない旅行やレジャーにお金を遣い、その借金がまだ残っているような場合には、間違いなく「負債」と見なされ、新たな融資を受けようとする場合においてはマイナスに働きます。
だから無担保のローンは、できるだけ持っていない方が良いのです。金利が高いだけでなく、使途によって信用を損なう恐れもあるからです。
但しこれは、金融機関によっても考え方に違いがあるでしょうし、その負債の額と個人の収入、購入する物件の規模によりバランスが変わってきます。
従って、まずはご自身の収入や預金・負債額等の資産を一覧化した「資産概要書」を作成し、いくつかの不動産会社にあたってみることをお勧めします。そのうちに良い対策が見つかるかもしれません。
事業を営むようになったら、
いかに借金を活用するか、
ということも重要な戦略になってくるのです。
頭金ゼロで7億の資産をつくる
桜木不動産投資塾
のホームページはこちら
関連記事
20代からの不動産投資は成功するか

最近は私の出入りしている不動産投資塾にも20代の方が増えてきました。
そんなに若いうちから始めたら、
きっと30代後半までには完全に時間的・経済的自由を手に入れて、
悠々自適の生活ができてしまうのでは、なんて羨ましく思ったりします。
ただ、私の周りにいる、不動産投資で輝かしい成果を収めている方々は、
もはやお金のために働くのではなく、
自分の使命としての仕事
を見つけている人がほとんどです。
だから会社に所属して雇われの身となって
がむしゃらに働くのではなく、
自分がやりたいことを
自己責任の上で全うしています。
時間的・経済的自由というものは
自分がやりたいこと
が先にあって
その上で自由を使いこなさないと
ただ無気力に、もしくはいたずらに
時間とお金を浪費するばかりになります。
20代のうちにそういった自分の目標が定まるのかどうか。
若いうちは不動産投資などしなくても、
もっと他にやるべきことがあるのではないか、
と思うのがオジさんの本音です。
自分が20代の時には考えもしなかった発想をする
若者へのヒガミなのミかもしれません。
そんな若いうちから、自分の目標と信念を
確立しているのだとしたら、それは本当に素晴らしいことです。
でも少しシビアなことを言うと、
資産家の御曹司でもない限り、
ごく一般的な20代では、
社会的信用が低いケースが多いです。
それはつまり、金融機関から何千万円、何億円というお金を貸してもらうことが難しい、
ということを意味します。
だからといって全く可能性が無い訳ではなく、
日本政策金融公庫という国がバックアップする金融機関では、
27歳以下を対象としたプランもあるくらいですから、
諦める前にいろいろ調べてみることです。
実は、
不動産事業を始めるのに理想的な年齢とは、
特にありません。
年齢ではなく、
勤務先、勤続年数、年収、自己資金の方がよほど、
金融機関からは重要視されます。
その点では、勤続15年以上の30代〜40代の方が融資を受けやすいことになりますね。
年齢が若く、勤続年数が短いのなら、
年収や自己資金でカパーすれば良いのです。
株やインターネットビジネス等で成功してまとまったお金を得て、
その資金を不動産投資に回す若い方もいらっしゃいます。
要するに、
全てが揃っていなければ始められないなどと決めつけず、
何かが足りなければ、他で補うようにすればいいのです。
但し気をつけていただきたいのは、
不動産事業は購入して終わりではなく、
その先の賃貸経営において絶え間ない努力
が必要になってきますので、
生半可な気持ちで始めると火傷をするかもしれない、
ということです。
夢と目標を明確に定めてから
スタートすることを、
どの年齢の方にもお勧めします。
頭金ゼロで7億の資産をつくる
桜木不動産投資塾
のホームページはこちら
関連記事
不動産投資では、どんな勉強をすればいいですか?

これから不動産投資を始めてみたいと思うのであれば、
まずは
不動産投資関連の本を2〜3冊
は読んでおくことをお勧めします。
本の題名は特に指定しません。
ご自身が興味を持ったタイトルのものを選べば良いと思います。
そしてその先、
5冊・10冊と読み進めていく必要はありません。
ほとんどの不動産投資本は、
きちんとした内容であればあるほど、
本質的な基礎知識に多くのバリエーションがないからです。
いろいろと難しいことが書いてある本もありますが、
そのほとんどが、実践の中で、身体で覚えていくべきものです。
基本中の基本の知識については、
2〜3冊読めば、書いてあることは大体同じです。
それでも表現の違いはありますから、
同じ内容のものを別の人の文章で読み返すと、
より理解が深まります。
そうして数冊読めば
理解出来る程度のシンプルな仕組みなのです。
そして不動産投資に関する書籍には、
大きく分けて
2種類のカテゴリー
があります。
一つは、
不動産会社の方が、自分の会社の宣伝も兼ねて、
できるだけお客さんを誘導して行こうという主旨もの。
もう一つは、
不動産投資で成功した人が、
自分の体験談をノウハウのように語るものです。
このどちらも参考になりますし
それぞれの「主旨」をきちんと理解して読み進めれば、
そこに書かれている内容がどんなやり方であろうが
混乱することなく、その本が伝えたいことと、
不動産投資の基本がわかるようになると思います
また、本を読むだけでなく、
セミナーに参加されることも面白いです。
参加費が数千円の低料金か無料の場合には、
不動産業界の方、もしくは不動産コンサルタントの方が
自分の顧客を獲得しようという主旨のもの
が最も多く、
それはそれで、フィーリングが合えば
その先に進めば良いし、
業界の人脈もできるので
ほとんどの場合、メリットばかりです。
不動産会社が主催するセミナーでは、
終了後に面談がセットされていることも多いので、
そういう機会は積極的に活用し、
話を聞いてくることをお勧めします。
本で読む知識より、
人から直接聞く内容の方がはるかにインパクトが強いので、
そうやって身体で覚えていくのです。
面談の際、ご自分の
「資産概要書」
を持っていれば、
その先の展開が間違いなくスムーズになります。
もう一つ、セミナーに参加するメリットとして、
知識を習得するというよりも、
他の参加者から刺激を受けることの効果の方が大きい
かもしれません。
最近のセミナーは聴くだけでなく参加するスタイルが増え、
自己紹介などのコミュニケーションを通じて、
同じ境遇の人・同じ目標を持った人
に出逢えます。
その人達が頑張って成功している姿を見て、
「自分にもできる」と思うことが肝要です。
これはかなり有効なマインドセットになります。
そして、
不動産投資の基礎を学んだら、
あとは行動するだけです。
関連記事
不動産会社の人は自分で物件を買わないの?

収益物件の購入を勧める不動産会社の人が、
「これはお買い得ですよ」
と言っておきながら
自分で買わないのはおかしいじゃないか、
という意見を聞くことがあります。
確かに、そんなに良い物件で、絶対に儲かるというのなら
自分で買うはず、
と勘ぐる人がいるかもしれません。
この点について、私は自分なりに納得していることがあります。
まず、不動産会社の人も、キャリアの長い人や職務のポジションが高い人は、
収益不動産を1、2棟、持っている人がザラにいます。
ではなぜ、良い物件を片っ端から買い続けないのでしょうか。
それは、不動産投資があくまでも融資を引く前提で行われる場合、
例え不動産関連の会社とはいえ、その属性が特別高いわけではなく、
融資をしてもらえる金額にも限度があるからだと思います。
金融期間がお金を貸してくれるなら、どこまでもやりたい、
というのが不動産投資家の心理。
でもなかなか思うようにいかない、
もしくは実績を積み上げるまで時間がかかる、
というのは、サラリーマンである限り
ほぼ同じ条件なのでは、と思うのです。
業界には若い社員さんもたくさんいますが、他の会社と同じく、
年収や会社の規模、業務内容など、いわゆる「属性」が重要になり、
まだ高額の融資を受けるに足るキャリアを積んでいないこともあります。
実際、私の物件を斡旋してくれた社員さんは、
今は買えないけれど、いつか絶対買えるようにないたい
とおっしゃっていました。
買いたくても買えない、という状況ですね。
もう一つは、
不動産投資は「投資」であり、
リスクを伴うもの。
つまり貯金ではないので、100%確証ということはありません。
これは不動産会社さんが客に物件を売る時にも
同じことを言うと思います。
ですので、今、不動産投資をするべきか、
その物件を購入すべきかどうか、は
すべてその人のビジョンに委ねられます。
この人にとって良い物件が、
あの人にとっても良いわけではないということです。
そのリスクを冒すより、不動産売買で得らえる仲介手数料の方が
ずっと確定した利益が得られるのです。
従って、
「事業経営」という主旨で不動産業を始めた会社は
無理してリスクのある投資案件を自ら買い漁るのではなく、
きちんと斡旋して、その手数料で利益を上げる方が
継続的な事業モデルなのだ、
と思う次第です。
ですので、
この人、本気で良い物件だと思って勧めているのだろうか
ということに関しては
そういった感情的な基準ではなく、
きちんとデータで判断すべきだと思うのです。
そうして自分なりの正しい判断基準を持つことができれば
親身になって斡旋してくれる不動産業者の方と
出逢える確率も高まるのです。
関連記事
不動産投資の基本は「場所選び」から?

9月14日付けの全国賃貸住宅新聞に、
不動産投資の基本は場所選びから
というタイトルの記事がデカデカと1ページにわたって記載されていました。
「統計データを用いた市場分析が肝要」
というサブタイトルで、
国勢調査に基づく人口統計データ
各都道府県や市区町村別の将来推計人口データ
近隣施設や類似物件のデータ
その地域における賃貸物件の供給数や空室率のデータ
をチェックし、市場分析を行って、
その場所で物件購入や建築をするべきなのか、
辞めるべきなのか
の判断をしましょう、
とのことです。
ひえ〜、不動産投資って難しい。そんなのできないよー、
と思ってしまいました。
これは、
米国の不動産経営管理士資格に基づく市場分析手法
なのだそうです。
さすがはプロフェッショナルスキルの紹介コーナーに掲載されるだけあって、経営的思想が満載です。
不動産投資仲間の会話の中にもこのようにデータ分析が得意な方がいて、
◯◯エリアの◯◯率は◯◯なんだ
ということを自信たっぷりに語る人を見かけますが、
それが果たして「基本」や「本質」なのかは、個人的に疑問です。
例えば、ここ数年で開発された新興住宅地域で、
駅から徒歩5分のファミリータイプで築15年、
古くからの地主の相続案件で売り急ぎ、来月までの決済限定で
利回り12%
なんていう物件があったら、前述のデータをどう活用するのかなぁ、
などと考えてしまいますね。
確かに
学校・公共交通機関までの距離
騒音や暴力団系の施設の有無
病院やショッピングモール等の買い物施設
近隣の企業の従業員需要の有無
などは把握しておくべきですが、
それって「市場データ」という程にまで
追い込んで正確な数値で把握しておくべきもの?
という気がします。
私はサラリーマンとして営業や商品企画に携わった経験もありますが、
こういう市場データは、とかく行動を起こす前に大変な時間をかけて作り上げ、
みんなで会議の場で納得して実行を決断する重要な指標にはなるのですが、
計画が実行された後で、
その時の分析が正しかったのかどうか、
検証されることはほとんどありませんでした。
なぜなら、
施策実行後はまた次の施策を検討しなければならない
過去の実績を追いかけても、取り巻く環境の方が速く変わっており、
今後の参考にならない
となってしまうからです。
市場データ分析の必要性を否定するつもりは全くありません。
但し、
数値というものは
取扱い方・見せ方によって真逆の捉え方ができてしまう
こともあるので
素人の自己満足で終わってしまわないように注意が必要です。
重要なのは、この記事の筆者が
「日常から得られる感覚的な市場情報のみに頼るのではなく、定期的にこのような統計データを用いた市場分析を行ってはいかがでしょうか。」
と提案されている通り、
目に見える偏った事実情報を妄信するのではなく、
一歩ひいた観点での客観的データも合わせて把握する
のは大切なことだと思います。
何を優先するか、は人それぞれで構わないし、
同じ物件は二つとない
のが不動産ですから、
自分で納得し、自己責任の範囲でリスク回避しながら経営改善していくこと
こそが本質だと私は思っています。
そのためにも、不動産投資を通じて、
自分が何年後にどうなりたいか、
何をしたいのかが一番重要
で、全ての投資判断のベースになるべきだと考えています。
「不動産投資の基本は、目標設定から」
が私の持論です。
関連記事
不動産の融資で「借換」を狙うなら、やる気を見せない方がいい

金融機関から高い金利で融資を引いて物件を購入し、後から金利の低い他の金融機関に借換える、というスキームを目指す不動産投資家がたくさんいます。
金利を下げてもらえれば、月々の返済額が少なくなるため、それだけキャッシュフロー(利益)が増えるからです。低金利での融資は、いわば全ての不動産投資家が求めることになります。
私はかつて、
金利4.5%で借りていた3億円近くの融資を、
地銀で1.2%に借換えました。
しかし、これを実現するまでには相当の紆余曲折、悩み、落ち込みを経験しました。
はじめに訪問した銀行は、紹介してくれた不動産会社さんから「お墨付き」のところで、まず先方も喜んで借換えてくれるでしょう、というくらいの明るい見立てでした。
そこで私は、その銀行に気に行ってもらうため、猛烈なアピールをしたのです。
熱い言葉その1
「こらからもどんどん買い進めて事業を大きくしていきます!」
熱い言葉その2
「不動産投資に人生を掛けています!」
熱い言葉その3
「借換えてくれたら貴行をメインバンクにします!」
これで気持ちが充分伝わったと、やりきった気持ちで返事を待つこと、2ヶ月。
結果は予想に反して全く逆の答えが返ってきました。
回答その1
「現在の所有物件はリスクが大き過ぎます」
回答その2
「サラリーマンなのに融資額が大き過ぎます」
回答その3
「せめてあと5千万円くらい返済が終わってから来て下さい」
そもそも2ヶ月も返事を待たせる、という時点で、銀行が後ろ向きであることがわかります。
(当時は気づきませんでしたが)
そして、これらの回答から想定できる
銀行の立場で物事を考えてみると、
専門家でもない人が、そんなに多くの不動産を買って大丈夫なのだろうか
本業が疎かになってしまうのではないだろうか
ちゃんと返済できるのだろうか
つまり「リスク」についてどれだけクリアできるのか、というの視点で見ます。
ですので、
一生懸命やっている
とか
規模を拡大したい
などということには全く興味がないのです。
そのことに気づくまで、あと何行かで失敗を繰り返しました。
そしてようやく戦法を変える必要があることがわかり、最後にトライした地銀では、差全く逆の姿勢を見せることにしました。
姿勢その1
「私は空いた時間で不動産事業を営んでいます」
姿勢その2
「所有物件はほぼ満室稼働で、安定した利益を生み出しています」
姿勢その3
「借換は、返済力を高めるために必要なことです」
この最後の
返済力を高める
ということが、銀行が最も安心・納得するアピールポイントでした。
そして借換が成功し、結果的に年間265万円ものキャッシュフローが改善しました。
これは1億円くらいの物件を新規に購入したのと同じくらいの効果です。
銀行によって考え方・求められる姿勢は異なってくると思いますが、
基本は相手の視点で
「自分に何を求めているのか」
をよく考え、
出来る限り数字を使ってロジカルに伝えることが肝心なのです。
関連記事
不動産業界の厳しい採用事情

9月21日付けの賃貸住宅新聞に、不動産会社の新卒採用に関するニュースが載っていました。
今年から採用規定が変わり、従来は4月1日から各企業が採用活動を始められていたところ、それでは学生の本業に支障をきたすとのことで、8月1日からにしなさい、となったそうです。
これによって一番被害を被るのが中小企業で、今まではまず大企業が内定を終えてから、それにこぼれた学生を抱え込んで面接し、採用につなげられていたところ、今年は8月から一斉に就職活動を始めるため、大企業と競合しながら採用活動をしなければならなくなるのです。
一方、世の中の「内定式」は、昔から大体10月1日で、春からの入社受け入れ準備のために、これをあまり遅らせることはできないでしょう。つまり、8月1日から9月30日までの2ヶ月間で、熾烈な人材獲得競争が行われるわけです。
そのため、中小企業では、一旦内定を出しても、後から大企業の内定をもらってキャンセルが相次いでいるそうです。中には21人に内定を出したところが、8月に入って8人が辞退したところもあり、こうなると何人が採用できるのか、ますますわからなくなってしまいます。
その影響がかなり大きいのが
不動産管理会社
です。
住宅そのものはとても身近なため、学生にとって、
「受けてみようかな」
という入口の敷居はそれほど高くないのですが、
逆に他の会社と併願されることも多いようです。
そして興味深いことに、不動産管理会社の内定辞退をした学生の入社先を聞いたところ、
「地元の金融機関」
という答えが多かったとのこと。
地銀は親にとって最も安心できる就職先なんだとか。地銀も採用人数を増やしていることから、親の強い勧めもあって、内定が出ればそちらに流れていくようです。
また、一口に不動産業といっても、
ディベロッパー系やオーナー業、
建物を維持する管理受託や、
賃料の管理をするプロパティマネジメント、
そして仲介業などいろいろな種類があり、
学生にとっては
その違いや特性を理解するのは難しいそうです。
私がお願いしている客付け会社の営業マンは若い方が多いのですが、考えてみると土日はまず休みが取れないだろうし、週休二日制というのも、必ず守られているのかどうかわかりません。我々の気づかないところで過酷な労働をしていることもあるのかもしれませんね。
そう考えると、「他に行くところが無かったから」というような理由で働いている人がいたら、あまり生産性の高い仕事はできないんだろうな、と思ったりします。せめてもう少し、賃貸仲介業のステイタスが向上すればいいのに。
トレンディドラマの主人公の仕事にでもなって、カッコいい営業マンとか、憧れ的職業のイメージになれば、もっと活性化されるかもしれません。
いずれにしろ賃貸仲介業は、人の幸せに貢献するとてもやり甲斐のある仕事であり、
不動産オーナーは、人に快適な住まいを提供する社会的使命を背負っている、と私は自負しています。
ですので、オーナーにとって最も大切なパートナーである賃貸仲介業の営業マンには、ぜひともモチベーション高く、誇りを持って働いてもらいたいものですね。
関連記事