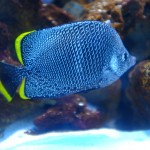物件売却時、売価と利益をどう考えるか? 最終回

収益不動産の「出口戦略」について、物件売却時の価格設定と利益確定をテーマで私の考察をお伝えし、今日で4日目・最終回となりました。
ちまたでよく耳にする
「◯◯円で買った物件を◯◯円で売った。だから◯◯円儲かった」
ということの真実を探ります。
ここでもう一度、売却時の利益の考え方について、これまでの考え方をおさらいしておきます。
案1:買った時の価格と、売った時の価格の差分で考える
単に購入価格と売買価格の差分が利益になる、という考え方。これは現金の売買時には通用しますが、実際には売買には仲介手数料を伴うため、この他に何百万円という支払いがある筈。
従って収益不動産の売買としては現実味がないのでは、との私見です。
本文はこちら。
案2.売却時の残債をリセットする、という目的で考える
収益不動産のほとんどは融資を受けて物件を購入しているので、売却時には残債をゼロにする、という考えに基づくケース。実際、
売却価格から仲介手数料を引き、残債を全て返したあとに残ったお金
が手元に残るわけですから、これを「利益」とする見方ですね。
本文はこちら。
案3.所有期間中のキャッシュフロー(インカムゲイン)と合わせて考える
残債をベースにいくら残ったか、もしくは残らなかったか、ということだけでは、長年の投資の成果を図ることはできません。家賃収入でローン返済し続けることのできる収益不動産では、収益物件から上がるキャッシュフローも投資の成果と言えます。したがって、
売買益(キャピタルゲイン)+月々の利益(インカムゲイン)
で利益をはかる、という考え方です。
本文はこちら。
さて、そして今回はいよいよ考察の最終回。
ここまでの3案も決して間違いではないですし、人によって捉え方も異なるので、どれを選べば正解ということもないと思います。この考え方を参考に、それぞれで一番納得できる方法を採用いただければ本望です。
●私の結論(案4)
売却時の利益を確定するには、売却価格から
残債をリセットして、諸経費を差し引いて残金を出し
インカムゲインを加えた後
「保険の返戻金」を加えて
購入時に拠出した「自己資金」を差し引く。
これで全てのキャッシュフローがはっきりと算出できます。
私が今回売却した木造アパートのケースでは、
- 購入価格:5,300万円。諸経費込みで5,600万円の融資を受けて購入。
- 自己資金はそのうちの100万円。
- 売却価格:4,900万円、残債4,700万円、諸経費200万円でプラスマイナスゼロ。
- 5年間所有したインカムゲイン:20万円
- 保険返戻金:150万円
ということで、
4,900万円(売価)−4,700万円(残債)−200万円(諸経費)
+20万円(インカムゲイン)+150万円(保険返戻金)−100万円(自己資金)
=70万円
となりました。
つまり、この木造アパートを5年間所有した結果として、70万円が手元に残りました。
これが今回の「出口」というわけです。
元々の購入価格5,300万円−売価4,900万円=マイナス400万円
とはだいぶ実態が異なりました。
私の売却の目的が「残債を無くす」ことにあったので、わずか70万円が残りましたがこれで良しとします。
そして、もしも売却時の価格が購入時価格を大きく上回り、残債をクリアしても数百万円・数千万円の利益が出た時は要注意です。
個人で所有している物件を5年以内に売却した場合、短期譲渡税として利益の39%を納めなければなりません。1,000万円の利益が出たら390万円が税金になります。
話が少々長くなり、ややこしさを感じてしまったかもしれませんが、収益不動産は
「安く買って高く売る」という単純な商売ではなく、
そこに手数料や自己資金、インカムゲイン、税金までさまざまな項目を捉えながら売買を行っていかなければならないのです。
こう考えると、売却によってよほど大きな利益を狙う目的がない限り、できるだけ長く所有して、継続的なインカムゲインを得ていく方が私には合っています。
4日間にわたり、お付き合いいただきありがとうございました。
頭金ゼロで7億の資産をつくる
桜木不動産投資塾
のホームページはこちら
関連記事
物件売却時、売価と利益をどう考えるか? その3

物件を売却した時、いくらで売ればいくらの利益が確定するのか、
というテーマについて私の考察をお伝えし、今日で3日目になります。
一日に一つずつ、考え方を整理しています。
そのきっかけは、私自身が木造2棟を売却するときに悩んだことがあるからです。
そして、周りの人や本で見かける人は、とても簡単そうに
「◯◯円で買った物件を◯◯円で売った。だから◯◯円儲かった」
というので、本当にそうかなぁ、と感じるのです。
それではまず、これまでの考え方をおさらいしておきます。
案1:買った時の価格と、売った時の価格の差分で考える
単に購入価格と売買価格の差分が利益になる、という考え方。
これは現金の売買時には通用しますが、実際には売買には仲介手数料を伴うため、この他に何百万円という支払いがある筈。
したがって収益不動産の売買としては現実味がないのでは、との私見です。
案1の本文はこちら。
案2.売却時の残債をリセットする、という目的で考える
収益不動産のほとんどは融資を受けて物件を購入しているので、売却時には残債をゼロにする、という考えに基づくケースがあります。
実際、売却価格から仲介手数料を引き、残債を全て返して残ったお金が手元に残るわけですから、これを「利益」とする見方ですね。
案2の本文はこちら。
そして3本目の今日は、もう少し広い視野で不動産投資を眺めてみます。
それは、一時の売買のみならず、所有していた期間のキャッシュフローを加味する考え方です。
たとえばその物件を5年間所有し、家賃収入から必要経費を引いて、年間100万円ずつのキャッシュフロー(手残り現金)を得ていたとします。
そうなると、たとえ売却金額から手数料と残債を引いた後に1円も残らなかったとしても、その物件を所有したおかげで100万円×5年=500万円が利益と考えることも正しいのではないでしょうか。
ちなみに、この家賃収入から得られる利益のことを「インカムゲイン」といい
売買の結果から得られる利益のことを「キャピタルゲイン」といいます。
不動産投資は、この「インカムゲイン」と「キャピタルゲイン」の両方を得られることを大きな特徴としている素晴しい投資スタイルです。
従って、やはり双方の利益を合算して捉えることが、出口(投資の結果)を見定める上では重要なのだと思います。
具体例として私のケースを挙げてみます。
① 5,300万円の新築木造アパートを、諸費用込みで5,600万円のオーバーローンで購入。
② 5年所有した後の残債は4,700万円
③ 売却時の価格は4,900万円(もっと高く売りたかったけれど残念!)
④ 5年間のインカムゲイン(家賃収入から必要経費を引いた手残り)は20万円(←寂しい)
この時、4,900万円で売る時の
仲介手数料(物件価格×3%+6万円)
諸費用(抵当権抹消手続き費用、日割り家賃清算時の買主への譲渡分etc.)
が合計で200万円でした。
つまり、4,900万円を買主さんからいただいて、仲介手数料と諸費用200万円を引くと、
4,700万円。これで残債を返済するとちょうどゼロになります。
ではこの投資では、プラスマイナスゼロなのか?
というとそうでもなく
所有していた期間のキャッシュフローが20万円あるのですから、
この投資の利益は20万円だった、としてみました。
「5年間、1円も出さずに最後は20万円の利益を得た」
要するに、キャピタルゲインとインカムゲインの合計で利益を確定させる、
という考え方ですね。
しかしこれでは、肝心の◯◯を忘れているのです。
いよいよ明日は最終章。
◯◯の答えと、さらに踏み込んだ私の結論をお話しします。
頭金ゼロで7億の資産をつくる
桜木不動産投資塾
のホームページはこちら
関連記事
物件売却時、売価と利益をどう考えるか? その2

昨日は、売却時の価格設定と利益の考え方について、案1をお伝えしました。
案1:買った時の価格と、売った時の価格の差分で考える
本文はこちら。
そして今日は、案2についてお話ししたいと思います。
案2.売却時の残債をリセットする、という目的で考える
購入時の金額よりも高い金額で売れた時、その差分が利益になるという考え方はとてもシンプルですが、その分が儲かった、というのは果たして正しいのでしょうか。
また、購入時に5,000万円で買い、売却時に4,900万円で売った場合、100万円マイナスだった、という考えた方は正しいでしょうか。
他の商品と同様に、もしも現金で売買が行われているのであれば、上記の考え方でほぼ正しいと思います。しかし、収益不動産のほとんどは、融資を受けて購入するものですから、残債を基準に考えることも大切です。
●売却目的によって売り方が変わる
実際、私の場合には、なかなか儲からない木造アパート2棟を昨年売却しましたが、その目的はキャピタルゲイン(売買価格の差分による利益)ではなく、
1.これ以上マイナスになることを防ぐ(ロスカット)
2.残債をリセットする
の2つが目的でした。
具体的には、5,300万円の木造アパートを、諸費用込みで5,600万円のオーバーローンで購入し、5年所有した後の売却時の残債は4,700万円でした。
この4,760万円をすべて返済して、残債をゼロにするためには、
4,700万円に売却時の仲介手数料ほか諸経費(約200万円)を上乗せして、
4,900万円で売却することが必要です。
つまり売価4,900万円が、残債をリセットするための「最低価格ライン」と言えます。
結果、この物件は5,000万円で売れました。
5,000万円から諸経費200万円と残債4,700万円を引いて、100万円が残ったわけです。
●ここから重要
従って、私はこのアパートを購入する時、1円も手出しが無くオーバーローンで取得し、5年間所有した後、売却して100万円の現金が手元に残ったわけです。
購入時の価格:5,300万円
売却時の価格:5,000万円
でも利益はマイナス300万円ではなく、プラス100万円。
5年間のローン返済は家賃収入でまかない、私は全く出費をしていません。
そして残った負債を売却によってゼロにし、かつ100万円の余剰を残しました。
これが、ローンを使って物件を購入することの、一つのメリットですね。
でも、5年間の不動産事業の結果として、果たしてこの100万円がすべて、と言っていいのでしょうか。
その答えは、明日に続きます。
頭金ゼロで7億の資産をつくる
桜木不動産投資塾
のホームページはこちら
関連記事
物件売却時、売価と利益をどう考えるか? その1

「出口戦略」という言葉があります。
不動産投資は買って終わり、というだけでなく、売却して初めて利益が確定することは周知の事実。
業界用語では、
家賃収入で得られる「インカムゲイン」ともう一つ
売却時の利益「キャピタルゲイン」
が重要と言われています。
では、ここで質問。
「売却時の利益」って何ですか?
買った時の金額と売った時の金額の差額?
それだけで、本当に「いくら儲かったのか」がわかるのでしょうか。
不動産投資家の皆さんなら、
物件の取得時にいろいろな税金や手数料がかかることをご存知ですよね?
では、真の「出口戦略」とは、いったいどんな指標を用いるべきなのか、
私の考え方を述べます。
案1:買った時の価格と、売った時の価格の差分で考える
例えば5,000万円で買ったものを5,300万円で売れば、
5,300万円−5,000万円=300万円の利益
という考え方。
これは最もシンプルで、ご自身の実績を語る人からよくこんな話を聞きます。
「去年5,000万円で買ったアパートが5,300万円で売れちゃってさぁ、300万円儲かったよ。」
このセリフの中で、本当に300万円儲かったのかどうかは疑問です。
なぜなら、購入時には物件価格×3%+6万円の仲介手数料を支払ったかもしれないし、売却時にも同じく仲介手数料を支払うケースが多いからです。
1.仲介手数料はいくらだったか
仲介手数料は、物件価格×3%+6万円かかるのが普通です。
5,000万円の物件を買うときは、5,000万円×3%+6万円=156万円、
5,300万円で物件を売る時には、5,300万円×3%+6万円=165万円となります。
従って、買う時も売る時も手数料がかかるなら、156万円+165万円=321万円を不動産会社へ支払うことになります。
2.不動産取得税を納めている
更に購入時には、必ず不動産取得税を納めています。
不動産取得税の税額は土地と建物によって大きく違いがあるので一概には言えませんが、ざっくり100万円だったとします。
そうすると、購入時には
5,000万円+156万円+100万円=5,256万円
を支払っている筈です。
その物件を売却時に5,300万円で売れば、165万円の仲介手数料が経費としてかかっていることになるので
5,300万円−165万円=5,135万円が手残りになります。
※計算を簡単にするために、他の諸経費(抵当権設定費等)は考えないことにします。
3.まとめ
ここまでの話をまとめると
5,000万円で買った物件を
5,300万円で売ったとしても、それは
5,256万円かかって手に入れた物件を、
5,135万円で手放した
と同じことになります。
これをもとに再計算すると、
5,135万円—5,256万円=121万円の赤字
となりました。
逆に、5,256万円かかって手に入れた物件を、売る時にプラスマイナスゼロにするには、
売却価格が最低でも5,425万円であることが必要です。
念のため検算すると、
5,425万円の仲介手数料(3%+6万円)=169万円
5,425万円−169万円=5,256万円(手残り)
ほら。ですので、
5,000万円で購入した物件は、5,425万円で売って、やっと利益0円なのです。
シンプルに「現金で売り買い」した場合には、恐らくこのケースに当てはまると思います。
しかし、ほとんどの方は融資を使って物件を買っているでしょうから、必ずしもこの考え方が正しいとは限らないのです。
融資を引いて購入した場合の出口(売却時の利益確定)については、
明日またお話しします。
頭金ゼロで7億の資産をつくる
桜木不動産投資塾
のホームページはこちら
関連記事
不動産投資ではなぜ札幌がオススメなのか?

都心ではすっかり利回りが低くなり、地方物件といえど、この1〜2年で利回り10%を切ることが珍しくなくなってきました。そんな中、相変わらず札幌エリアが注目されているようです。
しかし、札幌の不動産投資についてはさまざまな意見があり、
「競争が激しく空室が多い」
「入居者を入れた時の広告費(AD)は3ヶ月が当り前」
「雪対策で管理費がかさむ」
等、否定的な意見も少なくありません。
ところで今日は、ある不動産業者が主催するセミナーに参加しました。
そこでゲスト講師として講演されていたN氏は、国内外に約30億円の投資をされ、年間家賃収入3億円という強者です。
そのN氏がご自身のセミナーの中で
「今、日本で最もおすすめのエリアは札幌市内」
と断言されていましたので、その理由につき、ご紹介しましょう。
●札幌エリアの魅力
1.北海道最大の政令指定都市で、今後も人口減のリスクが少ない。
現在の人口は190万人で、今もなお微増。
地下鉄をはじめとするインフラが充実しており、今後人口減にも強いそうです。
特に中央区は2035年まで増加傾向、とのことです。
北海道の中でも札幌市、札幌市の中でも中央区。
逆に、このエリアを外すと、
いわゆる前述のネガティブ要因が勝ってしまい、
良い結果が得られ難いとのこと。
「札幌市」というだけでなく、より狭いエリアに注目していく必要がありそうです。
2.土地/建物の価格バランスが素晴らしい。
固定資産税評価額の内訳(土地:建物)が、
都心の場合には5:5から4:6であるのに対し、
札幌は25:75、20:80というケースが多いとのこと。
このように固定資産税評価額の中で建物比率が高いと、
売買価格に占める建物価格も比例して高く設定できます。
建物価格が高いと、
「減価償却費を高く取れる」
「消費税還付の場合、額が大きくなる」
などのメリットがもりだくさん。これは確かに魅力ですね。
また、建物単価と銀行評価額が近いため、フルローンが出やすいそうです。
全国規模の金融機関ではR銀行が特に積極的だとか。
3.アウェイ感が少ない
これは面白い発想です。
関東・関西の投資家にとっては、地方で物件を取得し、現地の管理会社の方と話をする際には、その土地の言葉を使いこなさないと、コミュニケーションが取りづらいことがあるとおっしゃっていました。
ところが札幌ではほとんどの方が標準語を話されるので、その問題がありません。
実際、北海道でNo.l規模を誇る管理会社では、管理物件の約85%のオーナーが首都圏在住というのには驚きました。
4.2026年冬季オリンピック、北海道新幹線延伸により更に注目される。
これはご本人の期待を込めた予測ですが、オリンピックの開催地に選定されることを夢見て、わくわくしながら物件を所有されているそうです。
こういう先読みが投資家の醍醐味でしょうし、楽しみながら物件を所有する余裕も大切ですね。
このような話を聞くと、札幌での物件所有も前向きになります。
そして更に、ここでネガティブ要因についても実感を込めてお話しいただければ、それを踏まえた上でまた説得力が増したでしょう。
いずれにしろ不動産投資に万全・保証はないし、思い通りにいかないことの方が多いのが現実ですが、それらを事前に回避したり、何かあった時にリカバリーすることが、投資家としての真の腕の見せどころだと思います。
札幌市中央区、マークしておきます。
頭金ゼロで7億の資産をつくる
桜木不動産投資塾
のホームページはこちら
関連記事
Air bnbはこれからどうなっていくのか?

先日、空室を短期間で旅行者に貸し出すサイト・Air bnb(エアービーアンドビー)について基礎知識を解説し、現在の私の考えを書きました。
Air bnbとは、いわゆる「短期貸し」のシステムを持った部屋の所有者と、国内外からの旅行者を結びつけるサイトです。不動産オーナーとしては、空室を旅行者に貸し出すことで効率よく賃料を回収できるというメリットがあります。前回のブログはこちら。
この度、取引の管理会社から新しい情報を入手しましたのでシェアします。
●短期部屋貸しの需要に関する市場背景
・一昨年あたりから外国人旅行客に対して政府が力を入れ、旅行客が増加している。
・特に都市部のホテルなどは稼働率が上がり、宿泊料も上昇傾向。
・今後東京オリンピックを控えてますます宿泊不足が懸念される。
そして、政府は東京などの国家戦略特区に指定された地域で、次の条件をクリアすれば宿泊営業を認めることになっています。
●自治体が認める短期宿泊施設の条件(要約)
1)7〜10日以上の宿泊期間を設ける
2)居室の床面積が25㎡以上
3)出入口及び窓は、鍵をかけることができる
4)出入口及び窓をのぞき、居室の境は壁作りであること
5)適当な喚起、採光、照明、防湿、排水、暖房及び冷房の設備を有する
6)台所、浴室、便所及び洗面設備を有する
7)寝具、テーブル、椅子、収納家具、調理のために必要な器具または設備
及び清掃用具を有する
8)施設の使用開始時に清潔な居室を提供する
9)施設の使用方法につき、外国語を用いた情報提供(案内)
こうしてみると、賃貸アパート・マンションではほとんどの条件を満たしているものの、やはり7)の家具設備は新規導入しなければなりません。
9)の外国語を用いた情報というのも、説明書作成にひと仕事必要になってきますね。
●利用者とオーナー双方にメリットがある「短期貸し」
但し、東京のビジネスホテル利用がワンルームで1泊1万円とした場合、短期滞在の料金はその半額程度だったりしますので、5,000円で10泊された場合に5万円。
それだけで1ヶ月分の家賃に相当する収入が入ってくる可能性もあるので、利用者にとっても格安感があり、オーナーにとっても効率よく収入を得ることができます。
また、ホテルと違って1部屋単位で料金設定されるため、二人以上で利用すれば更にお得である点も、利用者の注目を集めているようです。
●これから日本に来る外国人旅行客
2011年 623万人
2014年 1,341万人
2020年 2,000万人
という勢いで増えていくと予想されています。
この流れから、短期部屋貸しの需要はますます増えていくという予測です。
この方式で、果たしてオーナーが空室をカバーしていくことができるのでしょうか。
それは立地にも寄るところが大いにあると思うし、設備導入によるコストアップ、そして回転率の関係も重要になってきます。
今のところ、この「短期部屋貸し」のシステムが不動産オーナーにとってどうなっていくか、全くの未知数です。しかし、今回の記事には興味深い例が載っていました。
それは、コインパーキングです。
●コインパーキングの需要創出
バブル崩壊前までは概ね駐車場といえば月極(月ぎめ)でした。しかし、「短期時間貸し」というコンセプトのコインパーキングが出来てから、小さな土地でもコインパーキングで収入を得ることが可能になりました。これは利用者と土地オーナーの、需要と供給がピッタリ合ったビジネスモデルなのだと思います。
これからの賃貸経営も、そういった世の中の動向に対して柔軟な発想でついて行かねばなりません。あと一年もしたら、先駆者が取り組んだ結果(収支)を実績数値で示してくれる日が来るでしょう。私はその時期まで様子を見ることにしています。
頭金ゼロで7億の資産をつくる
桜木不動産投資塾
のホームページはこちら
関連記事
不動産投資で子どもの夢を叶える

不動産投資を続けていくために最も大切なことは、目標・目的を持つことです。
私がこの世界に入り、これからも継続していく理由は、家族の夢を支えるためです。
●娘の夢を叶えたRCマンション
不動産投資を始めた頃、長女が高校に入学する年齢で、その時に一年間アメリカに留学できる高校に進学したいと言われました。その費用が1年間で500万円。普通のサラリーマンではかなりハードルの高い金額です。
それでも私には不動産収入があったので、「何も心配せず行って来なさい」と言うことができました。
おかげで娘は英語がペラペラになっただけでなくホームステイを通じて多くのことを学び、帰国後も英語を活かした道に進もうと努力しています。
RCマンションを取得したおかげで娘の人生が拓けました。
●息子の志望校
そして今日は長男が高校受験を控え、志望校の見学に行って来ました。
娘の時もそうでしたが、私立高校はどこも感じが良くて驚きです。
・施設がキレイで学校全体が明るい雰囲気
・先生のプレゼンテーションがうまい
・生徒が温厚で真面目
たまたまそういう学校に巡り会ったのかもしれませんが、これまで見学した3校はどこも同じように、上記の3要素を備えていました。
私自身は高校までずっと公立で過ごしたので、当時、私立に通う人はどこか偏った教育を受けさせられるのでは、と勝手な先入観を持ち、あまり必要性を感じませんでした。
しかし、親になって初めて私立高校というものを内側から知り、そんな考えはガラッと変わりました。
今日見学した学校には地下に温水プールがあり、グラウンドには人工芝が敷き詰められています。希望者には短期留学のコースも準備され、図書室には5万冊の蔵書、コンピューター室には100台のパソコンが自由に使えるようになっています。
そしてこの学校は大学の附属高校なのですが、育成方針は
「大学の先にある人としての在り方・生き方を学ぶ」
ということだそうです。
こんなしっかりした学校に通える子供が羨ましいくらいです。
学力的には中堅校ですが、そんなことは説明を聞いている限り関係なく、一人一人が自分の可能性を試す選択肢が多い方がいいし、充実した設備と環境が整っている方が断然いいのでは、と感じた次第です。
●肝心なのは本人の意思
そして、子供がどこの学校を選ぼうとも、「お金が無いから諦めてくれ」、とは言いたくないという思いがあります。自分が貧しい家庭に育ち、あまり選択肢が与えられなかったことを振り返ると、自分の子供たちにはできるだけ夢や目標をサポートしてあげたい、そんな思いで不動産事業にチャレンジしています。
しかしこの学校選びもまた、子供本人の目標が第一です。自分の意思で選び、自分で努力するようにならなければいけません。親はあくまでもサポート役なので、その役割を全うすべく、私は今日も不動産事業に取り組みます。
私には私の目標があり、子供には子供の目標がある。それを家族で共有しつつ、お互いを励まし合っています。
頭金ゼロで7億の資産をつくる
桜木不動産投資塾
のホームページはこちら
関連記事
賃貸マンションの電灯をLEDに変える効果とは?

収益物件の電気料金を削減する一つの施策として、照明をLEDに変えることがあります。
但し、照明はまさに物件によってマチマチですので、一概にいくら削減でき、何年で回収できるかということは言えません。
ただ、LEDは従来の電灯よりも何倍もの寿命があり、環境によっても異なりますが、大体10年は交換しなくて済みます。この点、電球の交換費用も少しは考慮に入れて、単に電気料金だけではない節約効果を見込みます。
参考までに、私の物件のシミュレーション例を申し上げます。
A棟 電気料金 167,534円 → 50,168円
ランプ交換 20,530円 → 0円
合計 188,064円 → 50,168円 年間削減額 137,896円
B棟 電気料金 172,886円 → 102,295円
ランプ交換 11,940円 → 0円
合計 184,826円 → 102,295円 年間削減額 82,531円
2棟合計すると220,427円の料金節約になります。
LEDの導入費用を考慮すると、大体5〜6年で回収できる計算です。
しかし、お気づきのようにA棟とB棟では従来の電気料金はさほど変わらないのに、節減効果はA棟の方が大きくなっています。それは電球のタイプや個数によっても変わってくるからです。そう考えると、やはり個々の物件での判断が必要でしょう。
また、同時に検討したC棟は、今回、導入を見送りました。
C棟 電気料金 67,487円 → 30,675円
ランプ交換 4,190円 → 0円
合計 71,677円 → 30,675円 年間削減額 41,002円
実は、A棟とB棟にはエレベーターが設置されているため、電子ブレーカーの導入と合わせてLEDを入れました。これにより、削減効果を合わせて測ることができるからです。
しかしC棟はエレベーターも立体駐車場もなく、電気料金の削減余地が見込めなかったので、電子ブレーカーを導入しませんでした。従って、LEDを導入するなら単体で経費対効果を見なければなりません。
そうした時に、年間約4万円の削減効果は、償却まで7年以上経たないと設備投資の回収ができないシミュレーションでした。
そして何より、C棟は取得以来、ほぼ満室経営ができています。つまり、現状の照明を交換することがそのまま客付けを促進するとは考え難かったのです。
このように、今すぐに必要性を感じない場合には、数年見送って、さらに良いものが出るまで待つ、というのも、一つの経営判断だと思います。
さらに、LEDは電力量削減だけでなく、二酸化炭素排出削減効果もあり、見た目にも美しいデザインのものが多いので、オーナーとして物件のバリューアップに取り組んでいる姿勢をアピールすることもできます。
入居者によって受け止め方はさまざまでしょうが、電球が切れて管理会社に連絡する手間も省かれるし、最新設備を導入する大家さんが、悪いイメージに取られることはないと思います。仮に物件を売却する際にも、LEDを導入済みであることは好印象に受け止められると思います。
LEDの取扱い業者は、電子ブレーカーよりもメジャーな分、数多く存在します。費用は決して安くないので、見積は1社だけでなく複数の会社にお願いした方が納得感も得られます。但し、こちらも現場確認をしっかり行った上での提案でないと、シミュレーションが狂ってきますので、管理会社への連絡を含め、手間をかけて丁寧に対応しましょう。
頭金ゼロで7億の資産をつくる
桜木不動産投資塾
のホームページはこちら
関連記事
物件を購入したら、経営改善のためにガス設備をチェック!

物件を取得後の経営改善のために、まず私が最初にチェックする設備は、ガスです。
都市ガスかプロパンガス(LPガス)か、を確認するところからスタートします。
その物件が都市ガスを採用している場合にはプロパンガスへの切替、既にプロパンガスを使用していれば、別のプロパンガス会社への切替を検討します。
都市ガスはこれまで公共料金として提供されていました。そこに一般企業のプロパンガス会社が参入し、いろいろなサービスをつけて顧客獲得をしている、というのが業界の仕組みです。
入居者目線では、まず一般的な印象として、
「都市ガスの方が安い」という定説があります。
だから入居者さんも「ガスは都市ガスに限る」と指定して部屋探しをする人も少なくありません。
それを感じている管理会社も、都市ガスの方が客付けしやすいと思っているセールスさんが少なくありません。
でも、日本企業を舐めてはいけません。単に価格が安いだけの都市ガスに対し、黙って指をくわえて見ているだけのはずがないのです。
2016年からは電力市場の完全自由化が決定しており、更に都市ガスも2017年に全面自由化が予定されていますので、そうなるとますますエネルギー業界全体で熾烈な競争が予測されます。
例えば、ガス設備の中で最も修繕リスクが高いのが給湯器の交換です。大体10年〜15年くらいで交換の時期がやってきます。世帯の大きさによっても異なりますが、その費用は10万円〜15万円程度。これが徐々に部屋数分だけかかってきますので、30室ある場合には300万円〜450万円を将来の修繕費にあて込んでおかなければなりません。
これがプロパンガス会社と契約すると、ガス会社負担にて交換できるサービスが付帯されてきます。プロパンガス会社としては、継続的に顧客を確保することができれば、給湯器を提供することは、それほどハードルが高くないのです。
プロパンガス会社は世の中に2万社以上あると言われ、その中でしのぎを削って顧客獲得しなければならないので、ガス会社さんも切替には積極的です。
また都市ガスは、万が一の災害時には供給が完全にストップしてしまいますが、プロパンガスは単独の設備を敷地内に有しているため、早く回復できる可能性があります。
この他、カラーモニター付きドアホンの設置やエアコンの永年無料交換などのサービス、オーナーへのインセンティブ(報奨金)等もありますが、あまり調子に乗ってあれもこれも要求すると、それは必ず入居者のガス料金に反映され、個々の負担金が上がります。やがてそれが不満となって退去を促す原因にもなりかねないので要注意です。
また、プロパンガス会社ならどこでも良い、というわけではなく、契約条件をしっかりと確認しないといけません。
私がかつて木造アパートを売却した際、新築での購入から2年ほど経っていましたが、管理会社とプロパンガス会社がグループ提携していたため、契約書上、どちらか一方を解除することができない内容になっていました。しかもプロパンガス契約を解除する場合には、残存の設備償却費用を負担しなければならず、それだけで240万円かかるとのことでした。
その木造アパートの買主さんがどうしても管理会社を変えたいと要望されたので、止むを得ずプロパンガスの設備費分、売却価格を下げて売り渡す羽目になりました。
このように、契約解除できない期間が設定されていたり、プロパンの設備に償却期間が設けられていて、解約時には一気にその分を負担しなければならないこともあり得ます。いつまでその物件の所有するつもりなのか、という腹づもりと合わせ、よく検討・吟味した方が良いです。
私が取引しているプロパンガス会社は、都市ガスから切り替える際、値段が高くならないことを条件にしています。そしてそれを入居者さんにきちんと説明してもらいます。
その上で、給湯器交換無料のサービスを付けてもらっていますので、オーナーにとっては交換費用を節約することができ、経営改善が図れます。
更に先般購入した物件では、ファミリータイプにも関わらず追い炊き機能がついていませんでした。これは客付けの際にかなり深刻な阻害要因になります。そこでプロパンガスのセールスさんに相談し、給湯器交換に加え、新規入居者から順次追い炊き機能を設置してもらうようにしました。これで新規募集家賃を5,000円アップし、現入居者さんには賃料2,000円アップを条件に、追い炊き機能追加を提案しました。
こうすることで部屋の価値も上がり、入居者の満足度も上がって、やがて家賃収入も増えます。但し、この進め方にはやはり管理会社とプロパンガス会社の理解と協力があってこそ成果を生み出すものですので、よい会社・信頼できる営業マンと出会い、自分の主旨・目的・希望をきちんと説明した上で推進してください。
頭金ゼロで7億の資産をつくる
桜木不動産投資塾
のホームページはこちら
関連記事
利回りが低い物件しかない時はどうすればいいの?

昨日のブログでは、最近の不動産市況について言及し、2015年のRCマンションの利回りが8%台になっている、というお話をしました。ほんの数年前、2012年あたりでは10%台が普通に出回っていたので、今はかなり物件価格が高騰している、と実感されている方が多いと思います。
2012〜2013年頃に不動産投資に取り組み、十分な基礎固めをされて今は悠々自適な生活を送っている人がたくさんいます。
そういう方が書かれたノウハウ本も多数出版され、
「根気よく探していれば利回りの高いものが必ずあるし、銀行もたくさん訪問すれば低金利で融資が引けるのだ!」
というご自分の実体験を熱く語る向きの内容を目にすることもあります。
●激変した不動産市場
しかし、たった1〜2年で不動産市場は随分と変わってしまいました。私はちょうどその端境期におり、2012年から本格スタートした物件取得活動では、最初の1棟だけは利回り11%だったものの、それ以降はどんなに一生懸命探しても、RCで10%を越えるまともな物件には出逢えていません。あったとしても全空室に近い状態とか、築45年など、どうやっても融資が付きそうない物件ばかりです。特に私はオーバーローンを原則としていますので、築年数や入居状況は融資金額と融資期間に大きく影響して来ます。
というわけで、どう探しても利回りが低い物件しかない場合、それでも購入したいと思う理由があるのなら、次の対策を頭に入れておいて、前に一歩踏み出す、というのも一つのやり方です。
●返済比率が60%未満であれば、購入に踏み切る。
返済比率というのは、家賃年収に占めるローン返済額の割合です。
例えば家賃年収が1千万円の時、
1億2,000万円の融資を3.5%の金利で35年借りた場合、
年間返済額は595万円になります。
こうすると返済比率が60%未満になり、15%程度の空室が出てもまだ持ち堪えられると思います。
この返済比率を実現するためには、
1.金利が高くても、できるだけ融資期間を長く取れるように交渉する
2.融資期間が延びないなら、できるだけ金利の低い金融機関を探す
3.頭金を入れて融資総額を減らす
のいずれかを選択するしかありません。
③ができれば始めから苦労しないと思うので、
やはり①か②を粘り強く探していくしかないですね。
●なぜ物件を買うのか
今後、利回りが下げ止まるのか、それとも更に下がるのか、誰にもわかりません。
しかし、不動産市場で最も強いのは「物件を持っている人」なのです。いつの時代も土地や建物を持っている人が、売買の優先権を握ります。
今、とりあえずある程度の妥協をしてでも物件を入手し、後から経営改善を進めることはできますが、今、物件を取得しなければ、一向に不動産投資をスタートできない、というのも事実です。机や本にかじりついて評論するだけでいるか、とにかく行動に移すか、その選択によって将来が変わってきます。
●今、やるべきこと
このように、利回りが低いから買えない、と諦めるのではなく、
今こそ金融機関の情報にもっと敏感・貪欲になり、不動産会社やその関連の人脈を丁寧に育てながら、いち早く良い情報をキャッチしていくように努めるべき時期だと思います。
頭金ゼロで7億の資産をつくる
桜木不動産投資塾
のホームページはこちら
関連記事
不動産投資は、誰にも知られずにできるのか?

サラリーマンにとって、副業を職場に知られずにできるかどうかは重要な関心事ですね。
しかし現実には、不動産投資をしているサラリーマンは全国に山ほどいます。
私がかつて所属していた不動産投資塾でも、80%以上がサラリーマンでした。
普通の会社員をしながら、その給料では自分の望む生活ができない、だからといってもう一つ別の職場を持つことなど到底できない。だからこそ、効率よく収入が得られ、比較的リスクが低いと言われている不動産投資の門を叩く人が多いのだと思います。
かくいう私もその一人です。
職場に勤務しながら、別に悪いことをしているわけでもないのに、もしも知られたらいろいろと面倒なことになりかねない、と思うのは自然な心理だと思います。
●家族にも気づかれずに?
「誰にも知られずに」というのが自分以外の人すべて、となると、ちょっと難しいかもしれません。また私の場合、妻が最大の味方になってくれていますので、妻に知られずに不動産事業をすることは考えられませんでした。
同居の家族がいる場合、細かい話ですが郵便物が届くので、全く気づかれないということは難しいと思います。そもそも家族に秘密にしてまで不動産投資をやる意味があるのか、というところから疑問ですが、もしもそうしなければならない事情を抱えている人は、保証人を必要としない融資を模索することになり、郵便物の送り先を自宅以外に設定するなどの配慮が必要になってきます。
●職場ではそれほど心配ない
別居の親兄弟や職場については、話す必要がなければそのままできます。
一番気になるのは「職場」だと思います。副業という名で禁止されているためにNGだと思われる方が多いようですが、実は不動産所得は遺産相続などで普通にあり得る副収入ですので、社会的におかしなことではありません。
あまり積極的にやっているように受け止められると「副業」と見られてしまうかもしれませんが、あくまでも「偶然に得た副収入源」と位置づけていれば、会社として禁止することはできないと思います。少なくとも自分から言う必要はありません。
勤務先の労働規約か勤務規定に「不動産で収入を得ることを禁止する」という文言さえなければ、まず大丈夫なのではないでしょうか。
●住民税額は経理部門に通知される
唯一のチェックポイントとしては、社員の確定申告の内容を細かくチェックするかどうか、という点です。会社としては、社員に給料を支払う際に源泉徴収を行い、年末に誤差を調整するという作業が行われます。
そこから更に、給与以外の所得がある人は、翌年の3月15日までに確定申告をしなければなりません。
そこで所得額が変更され、それに伴う所得税が変更になります。ここまでは自分で作業する範疇なので問題ないのですが、税務署から勤務先へ、所得額の変更が通知され、それに伴う「住民税」の変更も伝えられます。
住民税は、前年の所得額に基づいて、毎月均等支払いが原則ですので、勤務先の給与から天引きされます。従って、前年の給与が変われば当然「住民税額」も変わり、給与の支払い者に通知されます。
但し、その増減の内容が不動産所得かどうか、という細かいところまでは知らされませんので、そこを経理部に追求されるかどうか、が確認ポイントです。
副収入というのは、比較的たくさんの人が何かしらの事情で得ているケースも多く、その内容まで調査するからには、よほど社則で固く禁じられている場合だと思われます。
●事業家には仲間が必要
別の観点で、不動産事業は仲間がいた方が良いです。
いろいろな情報や体験を分かち合うことで、必ず自分の進め方の参考になります。そして時には助け合ったり、ともに遊んだりしながら情報交換をすることがとても有益な業界です。
この辺りが会社組織とは大きく異なる点で、不動産投資家は個人事業主の方が多いためか、新しい人脈を拓くことに積極的です。
必然的にいろいろなことを覚え、自分のビジネス拡大につながっていきますので、ぜひ一人で閉じこもらずに、オープンに活動されることをお勧めします。
頭金ゼロで7億の資産をつくる
桜木不動産投資塾
のホームページはこちら
関連記事
不動産収入は不労所得ってホント?

不動産投資を勧める誘い文句に
「サラリーマンのあなたも不労所得を手に入れて、自由な時間を過ごしませんか?」
というようなキャッチコピーを見かけますが、
私の実感としてはいささか違和感があります。
●投資という言葉の意味
自分のお金を何かに預けて、それを殖やしてもっと大きなお金を手に入れることを「投資」といいますが、その投資対象が土地やマンションなどの不動産である場合、それを「不動産投資」と呼びます。
何とまあ回りくどい言い方をしてみましたが、不動産投資は他の投資とは大きな違いがありますので、あえてこういう表現から始めます。
●物件を購入する醍醐味
例えば自分のお金が100万円あって、それで株や債権を買うと、その時の価値は100万円ですよね。でも不動産の場合、100万円持っている人が現金で100万円の物件を購入することはほとんどありません。100万円持っていても、1,000万円の物件を買えたり、もっと高額な物件を購入することができます。
極論すると、1円も持っていなくても、何千万円もの物件を購入できるケースもたくさんあります。
それはなぜか。
そう、銀行(正しくは金融機関)がお金を貸してくれるからです。
なぜ、銀行は不動産を買う人にお金を貸してくれるのでしょうか。
それは、物件自体が「担保」になるからです。
つまり、もしもその人がお金を返せなくなった場合、担保になっている土地と建物を取り上げて売却すれば、大体貸した分の金額くらいは回収できるから、
と踏んでいるからです。
●銀行の考え方
そしてもう一つ、不動産投資で特徴的なことは、所有している間、空室が出ないように工夫したり、建物をキレイに保って物件の価値が下がらないようにする努力が必要になります。
つまり、不動産投資は「投資」というより「事業」なのです。
銀行も、投資をする人になどお金を貸してくれる筈もなく、不動産経営をする人に、事業資金としてお金を貸してくれるのです。
銀行の目線からは、普通にお店を出して商売する人にお金を貸す場合、万が一その事業が失敗したら資金がゼロになって返してもらえなくなるリスクがあるけれど、不動産賃貸業の場合は、まず倒産することはないし、いざという時には担保があるからよほど安全だ、という考え方を持った銀行員も存在します。(私を担当してくれている地銀の支店長の言葉です)
●不動産事業の本質
ですので、不動産で「月収」を得ようとする人は、単に銀行からお金を貸してもらえば自動的に増えていくなどという「投資の概念」は捨て、基本的に「賃貸業を営む」という覚悟を持って臨むことをお奨めします。
「安く買って高く売る」という投資スタイルをお望みの方は、まさに本当の「投資家」となるべくたくさんの資金を用意された方が良いと思いますし、その場合には「月収」という考えは当てはまりません。
不動産経営とは、入居者というお客さんがいて、仲介業者、管理会社、設備業者、保険会社など、たくさんのビジネスパートナーとともに運営するれっきとした事業なのです。
だから私は、自分の活動を「不動産投資」ではなく、「不動産賃貸業」もしくは「不動産経営」と呼ぶようにしています。(タイトルは「不動産投資」の方がキャッチーなので使うことがありますが)
この観点から、不動産賃貸業は、やり方を間違えなければ着実に儲かるし、金融機関をうまく活用していけば成長させることもできます。
不労所得、ということを「働かずに得られる収入」と解釈するなら、それは預金や株、権利収入のことを示すのだと思います。
不動産事業はそこまで楽チンではありませんが、他の事業のようにがむしゃらにならなくても、僅かな勉強とツボを押さえたアクションで、ゆとりある時間と収入が得られるということは実感できます。
頭金ゼロで7億の資産をつくる
桜木不動産投資塾
のホームページはこちら
関連記事
不動産投資の基本は「場所選び」から?

9月14日付けの全国賃貸住宅新聞に、
不動産投資の基本は場所選びから
というタイトルの記事がデカデカと1ページにわたって記載されていました。
「統計データを用いた市場分析が肝要」
というサブタイトルで、
国勢調査に基づく人口統計データ
各都道府県や市区町村別の将来推計人口データ
近隣施設や類似物件のデータ
その地域における賃貸物件の供給数や空室率のデータ
をチェックし、市場分析を行って、
その場所で物件購入や建築をするべきなのか、
辞めるべきなのか
の判断をしましょう、
とのことです。
ひえ〜、不動産投資って難しい。そんなのできないよー、
と思ってしまいました。
これは、
米国の不動産経営管理士資格に基づく市場分析手法
なのだそうです。
さすがはプロフェッショナルスキルの紹介コーナーに掲載されるだけあって、経営的思想が満載です。
不動産投資仲間の会話の中にもこのようにデータ分析が得意な方がいて、
◯◯エリアの◯◯率は◯◯なんだ
ということを自信たっぷりに語る人を見かけますが、
それが果たして「基本」や「本質」なのかは、個人的に疑問です。
例えば、ここ数年で開発された新興住宅地域で、
駅から徒歩5分のファミリータイプで築15年、
古くからの地主の相続案件で売り急ぎ、来月までの決済限定で
利回り12%
なんていう物件があったら、前述のデータをどう活用するのかなぁ、
などと考えてしまいますね。
確かに
学校・公共交通機関までの距離
騒音や暴力団系の施設の有無
病院やショッピングモール等の買い物施設
近隣の企業の従業員需要の有無
などは把握しておくべきですが、
それって「市場データ」という程にまで
追い込んで正確な数値で把握しておくべきもの?
という気がします。
私はサラリーマンとして営業や商品企画に携わった経験もありますが、
こういう市場データは、とかく行動を起こす前に大変な時間をかけて作り上げ、
みんなで会議の場で納得して実行を決断する重要な指標にはなるのですが、
計画が実行された後で、
その時の分析が正しかったのかどうか、
検証されることはほとんどありませんでした。
なぜなら、
施策実行後はまた次の施策を検討しなければならない
過去の実績を追いかけても、取り巻く環境の方が速く変わっており、
今後の参考にならない
となってしまうからです。
市場データ分析の必要性を否定するつもりは全くありません。
但し、
数値というものは
取扱い方・見せ方によって真逆の捉え方ができてしまう
こともあるので
素人の自己満足で終わってしまわないように注意が必要です。
重要なのは、この記事の筆者が
「日常から得られる感覚的な市場情報のみに頼るのではなく、定期的にこのような統計データを用いた市場分析を行ってはいかがでしょうか。」
と提案されている通り、
目に見える偏った事実情報を妄信するのではなく、
一歩ひいた観点での客観的データも合わせて把握する
のは大切なことだと思います。
何を優先するか、は人それぞれで構わないし、
同じ物件は二つとない
のが不動産ですから、
自分で納得し、自己責任の範囲でリスク回避しながら経営改善していくこと
こそが本質だと私は思っています。
そのためにも、不動産投資を通じて、
自分が何年後にどうなりたいか、
何をしたいのかが一番重要
で、全ての投資判断のベースになるべきだと考えています。
「不動産投資の基本は、目標設定から」
が私の持論です。
関連記事
不動産賃貸業では管理会社が重要なパートナー

サラリーマンの傍らで不動産賃貸業を営んでいると、職場では話題にすることもできず、突然の電話が鳴ったりすると、席を立ってこそこそと話したりしなければなりません。
別に悪いことをしているわけではないので胸を張っていれば良いのですが、
さすがに本業の仕事の真っ最中に不動産の電話をするのは気が引けます。
そして万が一同僚や上司に知られたら、きっと多くの人から先入観や偏見を持って見られるようになり
「あいつ、カゲでうまいことやってんな」
みたいなことを思われるのは叶いませんね。
だから誰にも話せないのです。
サラリーマン大家とは、そんな孤独な稼業でありますが、
実際の賃貸経営においては、協力なパートナーがいます。
それは、管理会社さん。
管理会社の仕事は、家賃の受け渡しだけをするのではなく、
入居者の募集や建物のメンテナンスに至るまで、私たちの物件の経営自体を代わりにやっています。
月々家賃のほんの数パーセントの管理費で、これだけの仕事をしてくれるのですから、非常にありがたいことです。
ですので、物件を購入したら
管理会社は慎重に選ぶことをお勧めします。
管理費は家賃収入の何パーセント取られるのか
という観点だけでなく、
清掃・点検の内容、頻度
も、きちんと確認し、その会社から外注に出されているものがあれば
必ず数社に見積をとってもらってから、決めるのが良いと思います。
そして、こういった細かい連絡をする際、私たちオーナーは、
管理会社さんに
できるだけの敬意
を持って接するべきです。
サラリーマンの風潮として、とかく職場における上下関係や顧客関係を意識していると
ついついこちらがお金を払っているのだからと
「上から目線」「お客様意識」が働きがちです。
「なんで言ったことをやってくれないの?」
「すぐにメールの返信がないのはおかしい」
「話が違うでしょ」
というような気持ちは押さえ、たとえ本当にそうであっても、相手に通じていないときには、
こちらの伝え方が悪かったのだ、
と思うくらいがちょうど良いです。
逆に考えれば、管理会社だって、一つの物件だけを管理しているわけではないのですから。
いかに、自分の物件を大事にしてくれるか、
それはお金でも権力でもなく、相手を思いやる気持ちなのではないでしょうか。
大事なパートナーである管理会社を責めても、
オーナーにとって何も得することはないのです。
そのことを頭に入れながら、
クールに、的確に、
こちらの要望を伝える。
そして、
どうしたら気持ちよく協力してくれるか
を考えながら
発言・依頼をする。
これが経営者として、人を動かす時の留意点。
毎日が学びです。
関連記事
タイムシェアは、不動産投資と呼べるのか

昨年の夏、家族でハワイに旅行した際、1万円の商品券がもらえるというお誘いトークにつられて、オアフ島にあるマリオットバケーションクラブという高級リゾートホテルを見学に行き、そこのタイムシェアの権利を衝動買いしてしまいました。
「タイムシェア」とは、
一定期間の所有権を購入する
不動産の一種です。
私が購入したのは、ハワイ・オアフ島のコオリナ・ビーチリゾートという、ワイキキからちょっと離れたところにあるマリオットの会員制ホテルで、
2年に一度、7泊分の権利
をもらえます。
部屋は完璧なオーシャンビュー(写真)で、
60㎡のコンドミニアムが2部屋つながっている、
合計120㎡のタイプです。
基本、会員制なので、一般の人は宿泊できません。
今のところ、日本人の比率は15%未満というところが、
とても外国らしくて気に入りました。
ちなみに同様のシステムで運営されるヒルトン・ワイキキのタイムシェアは、
約85%が日本人だそうです。
価格はおよそ400万円!
衝動買いにしては結構なお値段なのですが、これは「権利」なので、売却することも可能です。購入時にはちゃんと登記証明書も送られてきて、れっきとした「所有権」なのですね。
管理費としては年間12万円を毎年支払います。
でもこういうのは、金銭的な損得勘定では計れないものだと思っています。何より家族の前で、すっぱりと購入を決断したことで、お父さんとしては評価がグッとアップしました。
これで2年に一度はハワイに来れるし、マリオットグループと提携しているホテルは世界80カ国2900ヶ所以上にあるので、そちらにチェンジすることも可能です。
とにかく素晴らしいロケーションに加え、ハワイに旅行した際にホテルの予約でかなり苦労したので、これからは2年に一度、最高の場所、最高の部屋を確約されていると思うと、ちょっと優雅な気分です。
そして、場合によっては「7泊分」を自分で使わずに、賃貸に出すこともできます。通常では予約できないホテルなので、プレミアム感もあって人気が高いようです。この点、今流行りの“Air BnB” に似ているかもしれません。
私が購入を決断した際の、最後の一押しは、この物件が「商品」ではなく「所有権」であること。この所有権は相続もできるし譲渡・売却もできます。この感覚が、なんとなく不動産投資と似ているな、と思い、親近感を持ちました。
そうはいっても結局のところ、これを賃貸に出して利益を得る、というのは目的も逸脱していますし、そもそもそういう風に利用するためのものではないので、「収益物件」とは呼べないですね。
不動産投資家として、自分へのご褒美と、これからのモチベーションアップのための材料には有効なのかもしれません。
2016年の7月24日〜31日まで、このリゾートホテルで初めての利用を体験してきますので、まだ先の話ですが、その時にはまたレポートしたいと思います。
関連記事
これからの賃貸マーケット分析と「家賃」への対処

日本の総人口は2050年までに3300万人が減少すると言われています。
東京圏は今以上に「超高齢化」になり、なんと
4人に1人が60歳以上
になるそうです。
そんなにー?
と思ったりしますが、冷静に考えると、あと10年ちょっとすれば私も60歳以上になり、高齢化の一端を担う世代になるわけですから、とても他人事ではありません。
高齢化になると、お金を生み出す労働人口の数が少なくなり、逆に福祉や年金などお金をもらう人の人数が増えてくるので、若い人が税金をたくさん支払っていかないと老人を支えられない社会になります。
ではこういった将来の超高齢化を背景に、賃貸マーケットはどうなっていくのか、という点について㈱リクルート社が分析された内容についてご紹介します。
1.住宅着工数は増加し、空室が増える。
高齢者が多くなってくると、相続税対策のためにアパマンを建て、現金を不動産に変える人が増えます。
建設会社は当然、仕事が増えるので大歓迎。
結果として需要に対し供給過多になり、空室が増えることになります。
2.空室が増えると、募集条件がゆるーくなる。
必ずしも高齢化だけが原因ではありませんが、空室が多くなってくるエリアは、それだけ競合が増えるわけですから、入居者に選択されやすいようにサービスが良くなります。
その最も代表的で手をつけやすいのが
礼金・敷金
礼金ゼロ率は、東京23区外は引き続き上昇中です。
敷金ゼロ率は、神奈川・千葉・埼玉の場合、
2009年に10%だったものが
2014年では30%にもなっているそうです。
3.東京都の平均賃料は回復傾向
2009年のリーマンショック後からずっと減少が続いていた東京都の家賃相場は、2014年の年始より回復してきているようです。これもアベノミクスの一つの効果なのでしょうか。
このエリアに住みたい、という人が多くなれば家賃は下がらず、
このエリアは家賃が高いからできるだけ安い部屋がいい、もしくは隣りの県でいいや、
と思う人が多くれなれば、相場家賃も下がっていくのでしょう。
しかしまだまだ都内は根強い人気と需要が底堅い、ということです。
でも、私は東京都江戸川区にファミリータイプのマンション1棟(15戸)を所有していますが、昨年は1つの空室が7ヶ月も埋まらず、家賃を5千円下げてようやく決まった、という苦労をしました。更に来月はまた1室退去が決まっており、果たして家賃を下げずに埋めることができるのか心配です。
オーナーにとって、家賃の値下げは最後の手段。
その前に、
礼金をゼロにする。
敷金をゼロにする。
不動産会社に支払う広告費を増やす。
入居者が負担する初期費用をオーナー負担にする。
フリーレント(=一定期間の家賃無料)をつける。
これら単発のサービスを全て検討・実施した後、どうしても空室が埋まらない場合には、
家賃を下げるしかありません。
管理会社にとっては家賃を下げてくれるのが一番営業トークがしやすいと言われています。
高いと言われて他の会社の管理物件に行かれるよりも、なるべく今、検討しているこの物件に決めて欲しい時、「今なら家賃を◯◯円安くしますよ」というのは確かに殺し文句かもしれませんね。
でも家賃を5千円下げると、オーナーにとっては1年で6万円、2年で12万円の収入が減るのです。長く住んでもらえそうな物件の場合には、1ヶ月の家賃を下げるとそれが退去するまでずーっと影響します。しかも他の部屋もそれにつられてどんどん値段が下がっていくようになります。
ですので、空室を埋めたい時には、できるだけ家賃を下げずに入居者を決めてもらえるよう、管理会社さんにしっかりと理解してもらい、他の面でバックアップすることに注力されることをお勧めします。
関連記事
今、フィリピン不動産は「買い」なのか? 現地を理解するための10の基本情報

海外不動産投資に関心が高まっています。
その中で今最もホットな国は
フィリピン
でしょう。
かくいう私も、昨年の6月にマニラのグローバルシティという
銀座と六本木と表参道を合わせたような超一等地に
「プレビルド」のワンルームマンションを契約しました。
プレビルドというのは、完成する前に所有権を確保する方法です。
例えば私の場合、2018年に完成するまで毎月7万円を支払います。
頭金を積み立てて支払うイメージですね。
完成時に残金分を現地の銀行で融資してもらうか、
そのタイミングで値上がり幅が大きければ売却することも可能です。
それでは、これからフィリピンで海外不動産投資をやってみようという方のために
私が把握しているフィリピンの基礎知識・雑学をお伝えします。
1.東京から飛行機で4時間
アジア諸国の中でもかなり近い方で、所用時間で言えば日本国内を新幹線で移動するような感覚です。
2.人口は9,943万人(2014年IMFデータ)
マニラ市だけで2,129万人。
淡路島とほぼ同じ面積に東京(1,323万人)の2倍の人口。
それだけ人口が密集している、マーケットがある、ということになります。
3.平均年齢23歳
いわゆる「人口ピラミッド」という年齢別の人口分布図が非常に理想的で、多くの若い人が少ない高齢者の生活を支える図式が当分続くようです。
4.中絶禁止・離婚禁止
ASEAN唯一、93%がキリスト教徒の国。
更に離婚が禁止され、中絶も禁止されているため、
人口は今後も勢いよく増え続けると言われています。
5.公用語は英語とタガログ語。
英語圏からのアウトソーシング需要が莫大で、アメリカ・イギリス・オーストラリア等から英語でのサポートセンターとして活用。人件費が安いからですね。
6.平均月収は4.6万円
この金額は経済成長とともに急速に、確実に上がっていくと言われています。所得が高くなれば豊かな生活を送れる人も増えてくる可能性があります。
7.GDP成長率は7.2%。
2013年のGDP成長率は、アジアで唯一上方修正されて7.2%。
2010年以来の平均成長率は6.3%。
2020年くらいまでは相当の勢いがあると言われています。
8.出稼ぎ労働者が最大の輸出産業
労働人口の8人に1人は海外へ働きにでかけ、本国に送金しています。2013年度はわかっているだけで251億ドル(GDPの約10%)が海外からの送金だそうです。
9.Facebook利用率 93.5%で世界1位
携帯電話普及率は人口に対して107%。
それだけインターネット社会になっていて、情報の行き交いが活発に行われています。
これをビジネスに利用しない手はないですね。
10.カジノ大国になろうとしている
今、政府が国策としてカジノを後押ししています。
実際、フィリピンのカジノ産業は年率20%の伸びを続けており、これからはシンガポールを上回るカジノ大国になると言われています。
さて、私が購入したプレビルドの物件は、2018年の完成時、果たして物件価格が上がっているのかどうか。。。。
フィリピン不動産については、情報がどんどん増え、様々な憶測が飛び交っているようですが、あくまでも自分の目で見て、自己責任で判断しなければなりません。
でも、少なくとも私はこの投資経験で多くの人脈をに触れることができています。
更に、グローバルな視点を養う上でも、自分が物件を取得することでより親近感が増すこともあります。
ですので、
必ずしも金銭的な利益だけを目標にすることだけが不動産投資ではないのでは、と感じています。
常に良い点を見つけ、前向きに取り組んでいく癖を心がけたいですね。
関連記事
不動産投資で借金返済ができなくなる不安

まだ不動産投資の経験がない人、でもこれからできるならやってみたい、という人から、
「不動産投資をしたいけど、巨額の借金をするのがすごく不安」
という声を聞くことがあります。
たしかに不動産は人生で最も大きな買い物と言っても過言ではないでしょう。
融資額も何千万円、年億円もの金額になるのですから、
「万が一のことがあったらどうしよう」
「失敗は絶対に許されない」
と思うのも無理ありません。
不動産投資は「投資」であり「事業」ですから、
絶対に、100%安全保証、ということはありません。
「借金が返せなくなったら自己破産するのかな」
なんて、融資を受けようとする人なら、必ず一度はよぎる不安ですね。
しかし、不動産事業の場合、
銀行の目線においても、実際の事業運営においても
借金が返せなくて破産する
というリスクは極めて低いのです。
なぜなら、銀行は物件を担保に「不動産事業」に対して融資をするので、
万が一返済が滞るような場合には、その物件を取り上げればよい
という前提です。
そういう意味では
「飲食業など他の事業に融資するよりもはるかに安全」
と、ある銀行の支店長は言っています。
飲食業で、毎月安定的な売上を得るのは大変なことですし
そこから経費や従業員の給料を引いてローン返済に充てるのも
ひと苦労です。
ところが不動産事業の場合、
毎月の家賃が入ってくるのですから
急激に売上が下がることもありません。
ある程度安定した収入の中で、ある程度安定した経費を支払い、
毎月そのうちの何%かにあたるローンを返済していけば良いのです。
従って、不動産オーナーは、
空室などで家賃収入が予想を大幅に下回った場合には
手残りの現金は少なくなりますが、ローンが返済できなくなる程にまで
収入が減る、ということはまずありません。
また、そうならない物件を選んで買う必要があります。
そして、万が一家賃ではローン返済が賄えない場合には、
自分の持ち金から返済に当てなければならなりませんが、
いよいよお金が返せず、どうにもならなくなった時には
「物件を売却する」ことになるのです。
事実上は「銀行に取り上げられる」、ということですね。
物件を売れば融資額が全て返済できるか
という確証はありませんが、少なくとも銀行サイドでは
そういう見方をして融資額を決めます。
ですので、
担保価値が高い物件には多くの融資がつき、
担保価値が低い物件には始めから自己資金をいくら入れる、
という条件でお金を貸してくれます。
その結果、例えば1億円の借金が返せないから
全て自分で働いて1億円を稼がなければならない
という状況にはまずならないのです。
基本的に、ほぼ満室で経営していれば
ローン返済して充分にゆとりを持てる物件を買えばよいのですし、
所有してからも満室経営ができるように務めればよいのです。
そんなに難しいことではありませんので
どうかご心配なく。
銀行が充分に融資してくれる物件を掴むことができればこっちの勝ちです。
それができる物件を探す方がよほど大変だ、というのが私の実感です。
関連記事
不動産投資判断には「返済比率」にフォーカスせよ!

収益物件を購入する時、「利回り」よりも「借り入れ金利」よりも、ずっと意識するべき重要なポイントがあります。
それは
「返済比率」
です。
返済比率とは、
家賃収入におけるローン返済額の割合
を言います。
この返済比率が低ければ低いほど、賃貸経営はラクになり、多少の空室や修繕費が嵩んでも、ローン返済に対する不安が少なくて済みます。
逆に、返済比率が高いと、空室が出たり思わぬ修繕費がかかったりすると、家賃収入では返済ができなくなり、自分で身銭を切って支払わなければならなくなります。
ではそのとっても重要な「返済比率」について、もう少し詳しく解説しましょう。
例えば1億円の物件で利回り10%、年間家賃収入が1,0000万円物件を購入するのに、フルローンで1億円の融資を受けたとします。
家賃収入1,000万円に対し、
借り入れ金利が4.5%で融資期間が30年だった場合、
年間返済額は約608万円。
608万円/1,000万円 = 60.8%
が、返済比率となります。
返済比率が60%であれば、あと40%の余力がありますので、そこから管理費や修繕費、税金等を支払っても、少しは手残りがあるでしょう。
では同じく家賃収入1,000万円に対し、
借り入れ金利が4.5%で融資期間が35年の場合には
年間返済額は約568万円。
568万円/1,0000万円 = 56.8%
このくらいの返済比率になれば、まず大きな不安は払拭されます。
次に、また同じく家賃収入1,000万円で、
借り入れ金利が2.0%で融資期間が15年だった場合、
年間返済額は772万円。
772万円/1,000万円 = 77.2%
こうなってしまうと、収入の7〜8割を返済に当てていることになり、
1部屋でも空室が出ると、あっという間に赤字に転落する危険をはらんでいます。
つまりたとえ金利が低くても、借り入れ期間が短いと、年間返済額は大きくなり、
家賃収入に占める返済額の割合(=返済比率)が高くなります。
そして結果的に空室や修繕に対応しきれなくなる
ということになるのです。
ですので、
借り入れ期間はできるだけ長く取れる方が、
不動産投資には有利です。
今は物件価格が高騰し、なかなか良い条件で融資をひくことが難しくなっているとは思います。
本来ならば返済比率は
50%以下 が望ましく
45%以下 ならラッキー
40%以下 であれば楽勝
となりますが、フルローンやオーバーローンでこの数値になることはほとんどないでしょう。
また、
70%以上なら 考え直した方がよい
と思います。
こんな市況だからこそ、
金利が低くないとダメ
などと思わずに、
借り入れ期間を伸ばしてもらえるかどうか
にも着目してください。
返済期間が長くなる
=返済額が安くなる
=返済比率が低くなる
となりますので、
結果的に物件の収支が良くなるのです。
ここまででおわかりのように、
物件の収益性をみる場合には「利回り」や「金利」そのものを見ていても
あまり正しい判断にはなりません。
借り入れ金利と融資期間を把握し、
きちんと年間返済額を算出した上で
「返済比率」を見る。
これが最も重要な判断材料となるのです。
関連記事
投資判断における利回りと金利とキャッシュフローの関係

物件を購入する際、とかく「利回り」ばかりに気を取られていませんか?
不動産投資の判断で最も重要なのは「利回り」よりも「キャッシュフロー」なのです。
キャッシュフローの算出方法については前回のブログでお話ししましたのでご参照ください。
こちら。
さて、私たちが日頃「物件概要書」を目にするとき、まずは「利回り」の欄に着目します。
これは当然のことなのです。
では、その概要書に記載されている利回りが
11%だった時、「高い」→「買い」
8%だった時、「低い」→「見送り」
と判断するのは早計です。
なぜなら、投資効果を測るには「利回り」と「借り入れ金利」をセットで考えないといけないからです。
例えばフルローンの時、物件価格と同じ額を借り入れるとします。
その時、
家賃収入の利回りが11%で
借り入れ金利が4.5%だった場合、
11%−4.5%=6.5%
つまり6.5%がローンを引いた後の残りになります。
一方、
利回りが8%で借り入れ金利が1.2%だった場合、
8%−1.2%=6.8%
となり、6.8%が手残りになりますから、
利回り8%でも、借入金利によっては11%のものよりも利益が残ります。
同じ金利でも、返済期間が長ければ年間の支払額が減り、
利益が増えることになります。
物件によって、融資してもらえる金融機関が異なるケースでは特に
このようなことが起こります。
ですので、利回りを見た時に、
借り入れ金利はいくらか
返済期間は何年か
を合わせて考えておかないと、判断を誤ることがあります。
家賃収入からローン返済額を引き、
更にそこから管理費や税金等の必要経費を差し引いた額が
「キャッシュフロー」
となり、これが実際の利益を意味します。
ですので、物件購入を考える時には利回りだけでなく、借り入れ金利と経費も合わせてシミュレーションし、「キャッシュフロー」をしっかり把握しておくことが大切です。
そして、利回りもキャッシュフローも、満室率100%の場合だけでなく、
95%・90%・85%
というように、
いくつかのケースを想定して算出しておいた方が良いでしょう。
満室率100%というのは、一年間で一度も入退去がない場合ですので、
実際にはそんなことは稀です。
85%、もしくはそれ以下の満室率で算出しておけば、
自動的に「空きが何部屋あると赤字になるか」が一目でわかるようになります。
また「キャッシュフロー」は、
家賃収入に占める割合(%)だけを見るのではなく、
金額の絶対値で把握することもできます。
現在の私の場合では
1億円の物件に対して200万円のキャッシュフロー
を一つの目安としていますので、利回りの大小に振り回されることはありません。
このように、キャッシュフローを正しく理解しておけば、購入後の経営改善や次の一棟を買う時にも大いに参考になり、客観的な判断ができるようになるのです。
関連記事