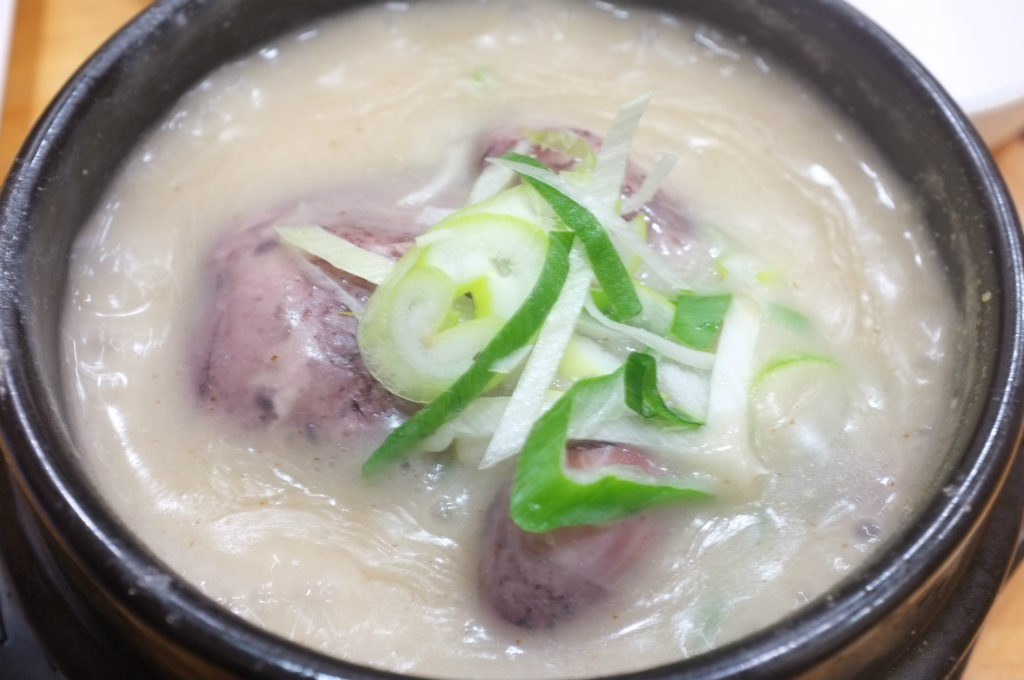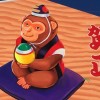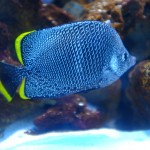不動産投資家はエリートか?

私は「エリート」という言葉がキライです。
子供の頃からクラスでは比較的優秀な方でしたが
何でもできるわけじゃないのに
何でもできそう
と思われて
良い子ぶっている
というイメージがあり
どこか皮肉めいた印象を
持っているからです。
私の中での「エリート」とは
裕福な家庭に育ち
親に敷かれたレールの上を歩き
良い学校・良い会社に所属して
世の中の表面的に恵まれた部分を
享受して
自己満足に浸っている
そんな人間を象徴していました。
しかし私は7歳の時に父親を亡くし
母親の女手一人で育てられたので、
家庭は貧乏でした。
小学校の低学年の頃から
家では内職を手伝い
高校時代には新聞配達のアルバイトをし
大学は夜学に通って
昼間働きながら学費を稼ぎました。
かろうじて大きな会社に入ったのも
大学を卒業して一年過ぎてからです。
そうして27年をその会社で過ごしてきた今、
年齢的に給料が頭打ちになり
手当もカットされ
もはや年収は増えるどころか
ガクッガクッと下がっていきます。
一方、優秀な若者たちはどんどん台頭してきて
活躍の場を求め、
会社としても年配者層には自主的に
退いてもらうような雰囲気を醸し出しています。
そんな状況の中、
先日、家族みんなで会話をしているとき、
子供たちから
「パパの考え方はエリートだね」
と言われました。
とっさに私は反応し、
「エリートなんかじゃないよ、何言っているんだ」
と返しましたが、
子供たちにとって「エリート」という言葉は
皮肉でも何でもないので、私のリアクションに
逆に驚かれました。
たとえばWkipediaには
「社会の中で優秀とされ、指導的な役割を持つ人間のこと」
とされています。
この言葉をそのまま受け止めれば、
子供たちの思いは純粋に
私への敬意を表した表現なのです。
さらに彼らが私のことをエリートと感じる根拠には
「周りの意見や環境に揺さぶられない、
本質を捉えた考え方を持っているから」
とも言っていました。
(実際はもう少し柔らかい言い回しでしたが)
自分の家族からそんな意外な指摘があり、
初めて自分がこれまで「意味のないこだわり」
に固執していたことを
思い知らされました。
自分の進路や人生の選択を迫られる時、
そしてもちろん不動産投資家にとっては
物件選びや
さまざまな業界関係者とお付き合いをする局面で
「自分の考えをしっかり持って相手に伝えること」
が重要です。
それにはいつでも「本質」を捉える意識が必要で、
多角的な観点と柔軟な発想が求められます。
さらには自分だけでなく、他人や周囲にも配慮して、
多くの人の幸せに貢献すること
これができる人を「エリート」とするならば、
私はいつでも人生のエリートでいたい
と
家族の言葉を受けて以来
思うことにしました。
表面的で浅はかな「エリート意識」は
実は自分の中にこそ埋もれていたものだと気づきました。
まだまだ、学びが必要です。
*****************
昨日のブログ
マイナス金利、不動産市場への影響は当面見込めず
*****************
桜木大洋のブログをもっと読みたい方へ
桜木不動産投資塾
のホームページはこちら
関連記事
マイナス金利、不動産市場への影響は当面見込めず
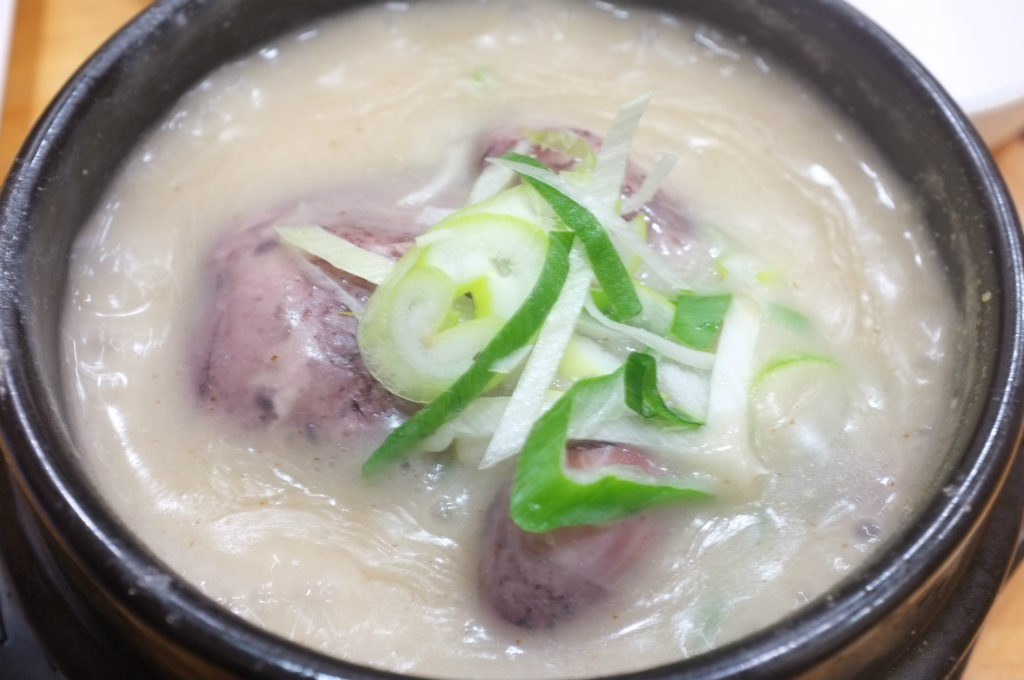
ちょっと前の記事になりますが、2/22・29付の週間全国賃貸住宅新聞に
2/16から始まった国内初のマイナス金利の影響についての考察が掲載されていました。
マイナス金利とは、
金融機関(銀行)が日銀に資金を預ける際の金利を
マイナスにするもの。
つまりお金を預ける時に
預ける側が
利息を支払う
という奇妙な仕組みですね。
そうすることによって
金融機関は日銀にお金を預けるよりも
企業や家計に融資する方が有利だと思い
積極的な融資を促されることが狙い。
銀行がお金を貸すことによって
モノの売り買いに弾みがつき、
経済が活性化するからです。
不動産業界でもこの動きに期待が寄せられ、
金融機関によって
金利が下がったり融資期間が延びたりする
ことがあり得ます。
しかしながら、融資条件が有利になっても
実際に新規購入者や買い増しなどの需要が増加するかは不透明
のようです。
「銀行は融資を増やしたいとはいえ
見境なく誰にでも貸し出すわけではない。
新規の需要が出てきたとしても、
リスクの高い投資未経験者に融資するとは考え難い」
(アイビー総研 関社長)
「今、不動産価格は高騰しているため
今購入できる人はある程度の資産を持っている人に限られる。
その点を加味しても、
初めて投資をする人が格段に増えるといったこともなさそうだ。」
(全国賃貸住宅新聞)
さらに
「不動産価格の高騰により、
ローンを組めない非正規社員の増加などを背景に
不動産に投資をしたい、という需要自体が減少している。
日銀はさらなる金利引き下げも検討していることから
今後の動向に期待したい」
(全国賃貸住宅新聞)
とありました。
つまり、マイナス金利だからといって
不動産投資をする人が急激に増えるとは考え難い
と述べています。
そのくらいの壁はあって当然だと思います。
でも、
知っているか知らないかで
得する人・損する人
がいるいことも事実です。
私の意見を付け加えると
融資が出やすくなる
ということは
売主から見れば
自分の物件を買ってくれる人
が増えるわけで、
そうなるとどうしても
値段を吊り上げられてしまいがちです。
買う側にとっては不本意なことでありますが、
欲しい人がたくさんいれば
物件価格は上がっていきます。
そうして高くなった
(=利回りが低くなった)物件を
購入して
しばらくは家賃収入で稼ぎ、
やがて値上がりするのを待つ
というのも一つの投資法です。
利回りばかりを気にしていると
何も買えなくなります。
銀行が融資に寛容になるということは
金利が下がる
返済期間が延びる
などの好条件が引き出しやすくなるので
利回りが足りない分は
金利と期間で吸収しながら
落としどころを見つけていくことも大切です。
不動産投資のスタイル
物件の選びかた
も、時代の流れとともに
柔軟に変えていくことが肝心ですね。
*****************
昨日のブログ
不動産投資家なら法人で車を買え!
*****************
桜木大洋のブログをもっと読みたい方へ
桜木不動産投資塾
のホームページはこちら
関連記事
不動産投資で相続税を考える

不動産投資は主に「税金との戦い」とも言われ、
税金対策をしっかりと行うことが、
不動産からの収益の行く先を左右する重要な要素になります。
それでも実は、
税金の軽減については国にから”オススメ”があるわけではないので
自分で調べるか人に尋ねるか
のいずれかの方法で能動的にアクションしないと
とても多くの税金を納める羽目になってしまいます。
数多くの税金の種類の中でも
多くの不動産投資家が気にしているものの一つに
「相続税」があります。
一方で、まだ相続したりされたりする案件が身近にない人にとっては
あまりピンとこないものです。
いずれにしろ、いつかはやってくる税金ですので
ここにカンタンに解説しておきます。
相続税とは、相続財産から非課税枠(=基礎控除)を引いた額が対象になります。
その「基礎控除額」が、
2014年までは
「5000万円+法定相続人一人あたり1000万円」
だったのに、
2015年から
「3000万円+法定相続人一人あたり600万円」
に減額されました。
つまり、控除金額が減った分、
より多くの税金が課せられるようになった
ということです。
これによって
従来は課税されなかった
5000万円くらいの財産を引き継ぐゾーン
例えば地価の高い都市部などで
対象者が広がっているようです。
また、課税財産額に応じた税率も
2015年から上がりました。
14年までは10〜50%の6段階でしたが、
15年から8段階に変わり、
以下の通りとなりました。
1000万円まで 10%
3000万円まで 15%
5000万円まで 20%
1億円まで 30%
2億円まで 40%
3億円まで 45%
6億円まで 50%
6億円超 55%
最高税率は55%。
シンプルに言って、
課税財産額が10億円の人は、5億5千万円も
税金を納めるのですねー。
しかしながら、まずその財産額とは、
固定資産税評価額が基準になります。
そして賃貸物件の場合、
借家人に一定の権利があるものと考えられ、
借家権割合30%を引くようにします。
そのため、建物は固定資産税評価額×70%になります。
いずれにしろ
不動産を持っているということは
財産を所有している、ということで
相続時には重い税負担を強いられるようにできています。
これをできるだけ回避するため
建物の評価割合が低い
タワーマンションの
特に高層階の購入を勧める業者も台頭してきています。
それがあからさまに節税対策であることがわかると
税務署からは「否認」されるリスクもあるようです。
税金はとても奥が深く複雑。
これでいい、と思っていても
税制は世の中の流れとともに必ず改正されますので
節税する資産家と、税務署の間の
“いたちごっこ”のようなものです。
決して安心せずに、常に税の情報には
アンテナを張っておくべきですね。
**********************
昨日のブログ
不動産投資家のコミュニティーには謙虚な人が多い?
**************************
桜木大洋のブログをもっと読みたい方へ
桜木不動産投資塾
のホームページはこちら
関連記事
不動産投資家は、急いだ方がいい?

収益不動産を探している人が、不動産会社を訪ねた時のNGワードは
「急いでいませんので」
という言葉です。
自分の希望や資産背景などを話し、
次に良い物件があったら案内してほしい、と
お願いする時です。
忙しい不動産会社の方にお願いをするのですから
こちらとしては気を使って
「急がないのでお時間のある時に」
と言いたくなってしまう気持ちもわかります。
しかしながら、収益物件に関しては
そんな風に遠慮をしていると
ずっと自分の分が回ってきません。
なぜなら、物件を欲しい投資家は
山ほどいるからです。
Amazon.comで不動産投資の本を検索すると
4,403件ヒットします。
それだけ不動産投資は多くの人にとって関心があり
そういった本を読みながら実にたくさんの人が
物件を探しているのです。
こんな不動産市場は当然ながら
「売り手市場」
になっています。
物件がどんどん高騰して
利回りが下がっている現状からしても
売りたい人より
買いたい人の方が
圧倒的に多い
ということが顕著にみられます。
この状態で不動産会社としては
まず収益物件を探すのにひと苦労、
そしてやっと見つけた物件は
あっという間に売れてしまいます。
そうなると必然的に
「今すぐ買いたい、買わなければならない」
という人を優先的に
案内したくなります。
悩んだりしているうちに
他の投資家・他の不動産会社に
買われてしまうからです。
ある意味
不動産会社も
客を選ぶ
というスタンスにならざるを得ません
私たち不動産投資家は
たとえ不動産会社のセールスさんが
どんなに低姿勢であっても
実は投資家を選んでいる
という事実を理解すべきですね。
ですので、少しでも物件を紹介してもらえそうな可能性があったら
「いつ返事をもらえるのか」
「いつ進展がわかるのか」
を常に確認するようにして
相手を追い込んでいく方が良いです。
ただし、既に有効な関係ができていて
自分のことをよく理解してくれている
という手応えを感じられるほど
懇意な相手であるならば、
信じて待つ
というのも一つの手だし
相手に信頼感を与える
という意味では
良い場合もあります。
その際にも
だいたいどのくらい待てば返事があるのか
くらいは事前に確認しておくべきです。
私はこれでも小心者で
電話をかけるとうるさがられるかもしれない
と思う時があります。
そんな時には
LINEメッセージ
を送ってワンクッションをおくようにしています。
LINEやメールであれば
相手が時間のある時に読めば良いし、
考えてから返信するゆとりがあるからです。
不動産会社さんとのやりとりには
人間関係・社会での仕事の進め方の
基本があります。
相手のことを思いやりつつ
自分の要望をはっきりと伝えること
この繰り返しが
やがて身を結ぶのです。
**********************
昨日のブログ
物件購入時は管理費を見直すチャンス!
*******************
桜木大洋のブログをもっと読みたい方のために
桜木不動産投資塾
のホームページはこちら
関連記事
賃貸業界商戦期にオーナーはどう動くか?

不動産賃貸業界の商戦期は1月〜3月。
学生や社会人ともに、入学や転勤の時期を迎え、新しい住まい探しが活発に行われる時期です。
賃貸不動産会社にとって、この時期は年間売り上げの半分を占めると言われています。
それだけセールスさんも忙しくなるため、個別の案件に細かく関わる時間も少なくなるかもしれません。
では、その商戦期の対策として、オーナーは何をすれば良いのか、考えてみました。
まず、昨今の部屋探しで大きな変化が見られるのは、
スマートフォンの急激な浸透です。
2011年の部屋さがしに使われた機器(複数回答)は
88.1% がパソコン
12.7% がスマホ
0.5%がタブレットでした。
そして2015年では
48.9% がパソコン
84.6% がスマホ
10.3% がタブレット
になっています。
約85%がスマホを使って
なんらかの部屋探しをしているということは、
もうほぼ全員がスマホを使っているような感覚です。
ユーザーがこれだけスマホを利用している中
自分の物件情報はスマホに対応しているか。
これをチェックすることが大切です。
物件情報は大抵パソコンで作成されるので
スマホ対応で見やすい画面設計になっているか
効果的な写真がうまく表示されるか
を見て、もしもスペックの一覧表などが
スマホユーザーにとって見難い仕様だと
どんなに中身がよくてもユーザーにスクロールされて
流れてしまうか、別のサイトに行かれる可能性が高くなります。
次に、最近のマーケット環境で大きな変化が見られるのは、
インターネット無料物件の急増です。
例えば東京都中央区では
2015年12月9日の全国賃貸住宅新聞の調べによると
SUUMOに掲載された物件の7.6%がインターネット無料。
新築に限っていえば20.2%にのぼります。
生活に欠かすことのできないインターネットが無料
ということは、
家賃が6,000円くらい安いのと同じ価値があります。
この状況は東京に限りません。
札幌市中央区では
掲載物件の8.3%がネット無料であり
新築では29.1%。
長野県諏訪市では
掲載物件の4.5%がネット無料で
新築ではなんと、100%。
中古物件のオーナーは、競合が新築物件では
それだけで不利になるにも関わらず、
さらにネット無料にされると
ますます家賃を下げるしか、対応策がなくなってしまうかもしれません。
この動きをどう読むか。
データはあくまでもデータですが、
世の中の流れを理解した上で
実際に所有物件の周りで何が起きているのか、を
きちんと把握することが大切です。
管理会社にも確認した上で、物件の現状を把握し、
設備投資を考えるよい機会になると思います。
(2016.1.4付 全国賃貸住宅新聞より一部抜粋)
*********************
昨日のブログ
不動産投資は他人のせいにしてはいけない
*********************
桜木不動産投資塾
のホームページはこちら
関連記事
不動産投資は他人のせいにしてはいけない

慣れないながらも不動産投資を始めている方は、
いろんな人に話を聞いたり、自分で本などを読んで勉強されている方も多いと思います。
そうして素直に行動して、
ようやく物件を買えた
でも実際に運営してみると
空室が出たり
修繕費がかかったりして
期待したより手残りが少ない
もしくは
もっと次々に物件を買いたかったのに
思ったより融資が通らない
良い物件が見つからない
そんな時、
やっぱりあの人の言うことを聞かなければよかった
なんて感じることはありますか?
でもそれは大きな間違いです。
不動産投資はあくまでも自己責任。
情報をもらったり
アドバイスを受けたりすることは
大いに必要ですが
最終的には自分の責任で判断し、行動しなければならないのです。
先日、私が対談した成功者の方の話によると
ビジネスで成功を収めるために大切な心がけは
・時間を無駄にしないこと
・他人のせいにしないこと
の2つだそうです。
時間を無駄にしないこと
については、その時のブログに書きました。
こちら。↓
成功する人の時間の過ごし方とは?
もう一つの
「うまくいかなくても他人のせいにしない」
ということについては、
人はつい、思い通りにいかない時に
自分以外のことに原因を探し出すものだけれど
それではいつまでも成長しないし、
根本原因がみつからないまま
ずっと変わらない自分と向き合っていく
ということです。
理想の物件が見つからないのは
不動産市況のせいじゃないし
良い物件に巡り会えないのは
仲介会社の営業マンのせいじゃなく
融資が降りないのは
銀行マンのせいでもなく
空室が出たり修繕費がかかるのは
入居者や管理会社のせいではありません。
すべて自分に原因があるのです。
そして、
もしも物件が買えて、しかも満室になった時には
仲介会社の営業マンと管理会社のスタッフのおかげです。
そう
「うまくいなかい時には自分に原因があり」
「うまくいった時は人のおかげ」
こう思うことが大切ですね。
これは単に心がけ、気持ちの持ちよう
というだけでなく、
そうすることによって
うまくいかない時は必死で対策を考え
うまくいった時には感謝の意を伝える
という具体的な行動に結びつくのです。
それを積み重ねることによって
経験やノウハウが蓄積され
やがて大きな結果へとつながります。
最初からすべてがうまくいき、
一度もつまづくことなく財を成す人なんて
ほぼ皆無です。
恐らく「成功者」と言われる人のほとんどは
この道を歩んできているのでしょう。
うまくいかない時こそ
信じること
行動し続けることが大切。
常にこんな前向きな気持ちで
歯を食いしばっていきたいと思います。
*****************
昨日のブログ
年のはじめは不動産投資家にとって復活のチャンス!
*****************
桜木不動産投資塾
のホームページはこちら
関連記事
不動産投資に必要な2つの柱とは?

これから不動産投資をはじめようという方、もしくは今もやっているけれど、なかなか思うように成果が出ないという方は、ぜひ次の2つのチェックをされてみることをお勧めします。
- 数字を使うこと
- コミュニケーション能力を上げること
このうち、「コミュニケーション能力をあげよう」
というのは、ほとんどすべての先生・先輩方が異口同音にして唱えることですね。
コミュニケーション力を高めるために
電話やメールをしたり
直接会って話したり
そしてそういう時には常に
相手の立場に立って
相手の気持ちを考えて
行動しましょう
なーんていう言葉をたくさん聞いてきましたね。
これはもう必要最低限のルールと言っても過言ではないでしょう。
すでにできている人もたくさんいるでしょうし、
完璧にできているということもなかなかないので
こういう言葉を聞くとまたインスパイアされて(=刺激を与えられて)
よーし、がんばるぞ、という気持ちになると思います。
しかしながら、今回特に力を入れてお伝えしたいことは
「コミュニケーション力」に比べて
やや忘れられてしまいがちな
「数字で把握する」
の方です。
ご自身の物件を、どれだけ数値で把握されているでしょうか。
昨年のキャッシュフロー目標はいくらで
着地はいくらだったか
を即答できる方がどれくらいいるでしょうか。
「数値で把握する」ということの意味は
利回りや
融資期間・金利
のことではありません。
それは購入時に参考程度で見るものです。
一番大事なのは
例えば一年間で把握する際、
・その年中に想定できる最大利益額はいくらなのか
を具体的に算出しておくこと。
・毎月、実際の家賃収入や必要経費をきちんと把握し、
予算との差分を理解しておくこと。
この2つが非常に重要です。
期待できる予算に届かない
という場合には
・空室が出て、なかなか埋まらない。
・思ったより修繕費がかかった。
・太陽光や電子ブレーカー、LEDなどの設備投資をした。
のいずれかが原因であることがほとんどのはず。
これらをきちんと把握していることで、
目標を立てて数ヶ月後に、
どんな対策をどれくらいの費用をかけて実行できるのか
が正確に判断できるようになります。
そして、翌年に向けた対策のために
しっかりとした根拠を持って費用負担(=投資)することが
できるようになります。
数値で把握してこその賃貸経営。
これくらいのこともやらずに
「購入した時は年間⚪️⚪️万円のキャッシュフローだったと思う」
「今年は若干の手残りがあったとは思うけど、厳しかったかもしれない」
「たぶん月何万円くらいのキャッシュフローだったと思う」
など、
「〜と思う」とか「〜かもしれない」なんて
曖昧なことしか把握できないのであれば
はっきり言ってこの先の発展は難しいです。
不動産賃貸業は、ほとんどの場合、
マイナスになることは稀なので
生活を脅かされるような心配はない反面、
もっと伸ばそう
と思った時にも感覚が鈍くなる人が多いです。
数値で本質を把握する
これが肝心なのです。
2016年のはじめに
所有物件の想定利益を把握するために
・家賃収入
・返済金額
・必要経費
・税金
のすべてを一覧表にまとめておくことをお勧めします。
私はすでに完了しました。
あとは予算達成に向けて、行動あるのみ。
一緒にがんばりましょう。
*****************
昨日のブログ
不動産投資家へのメッセージ 「成功」の反対は?
*****************
桜木不動産投資塾
のホームページはこちら
関連記事
不動産投資家へのメッセージ 「成功」の反対は?

新年あけましておめでとうございます。
家族のために戦う不動産投資コンサルタント・桜木大洋です。
今年も引き続き、不動産投資で人生を変えたい、家族の幸せを守りたい
そんなお父さんを応援します。
そして今年はいよいよ本を出版することになったので、
購入予約特典として、業界の著名人にインタビューした動画コンテンツをお届けしようと
昨年末はギリギリまで精力的に取材をしました。
その中で、一番印象に残ったことは
どの方からもメッセージは同じ。
不動産投資で成功するには行動あるのみ!
ということです。
これは自分でも実感することですが、
逆にこのように言いたくなる理由は、
「行動しない人が多すぎる」
からです。
不動産投資を志す人は、
比較的 有名な大学を出て
大きな会社に入り
平均以上の給料をもらっている
そんな人が多いです。
また具体的な学歴や職歴が関係なくても
頭の良い人
要領の良い人
真面目な人
勤勉な人
が興味を持って
この世界に入ってくるケースが多いのです。
そして、そういった優秀な方々は
ものすごい勢いで知識を得て
情報を吸収していくのですが、
実際に物件購入の局面になってくると
できない理由を並べてみたり
肝心なときに躊躇したりする人が
非常にたくさんいらっしゃいます。
不動産投資は
実際に物件を入手して運営したり
融資を受けてみなければ
理想的な結果が得られるかどうかは
わからないのです。
また、その年その年で所有物件にトラブルが起きたり
不動産市況全体が変わりますので
必然的に
得られる結果も変わってくるものです。
知識ばかりに詳しくなって、
不動産投資のリスクやデメリットを
必要以上に意識し、
一歩を踏み出せない人がどれだけいることか。
その現状を多くの先輩たちが嘆き、
「とにかく行動しないと何も始まらない」
というメッセージを声高に叫ぶのです。
成功の反対は、何だと思いますか?
とインタビューで逆に問われ、
私は正直言って戸惑いました。
「成功の反対は「失敗」と答える人が多いと思いますが、
失敗しているのは、前進しているのと同じこと。
成功するまでやり続ければ良いだけです。」
とその方は答えられ
「成功の反対は、行動しないことです。」
ときっぱり。
たしかにたしかに。
どんなに成功のスキルと知識を持っていても
物件を購入しなければビジネスは始まりません。
これまでの私も、うまくいかない毎日がずーっと続き、
それでも諦めずに行動し続けているので
なんとか順調な結果が得られています。
どこまでやれば終わり、
ということもなく、
自分の目標を達成するまで、
行動し続けることが
成功の秘訣ですね。
今年も前を向いて行動し続ける一年を。
*****************
昨日のブログ
不動産投資で成功する条件とは?
*****************
桜木不動産投資塾
のホームページはこちら
関連記事
こんな不動産投資家になりたい

年末になり、サラリーマンの仕事も休みに入りました。
残された年の瀬の日々を、今までできなかったことに費やしたいと思います。
会社に勤めていることで、今までできなかったこと
それは、ゆっくり考えることです。
1. この一年、目標を達成できたか。
→ 1棟買うことはできたけど、目標の3棟までは届きませんでした。
結果が全て、と言われるなら、努力が足りなかったと言わざるをえません。
でもそれで後悔しても仕方ない。
なぜ目標を遂げることができなかったのか、
それを考え、次につながるアクションをするしかないのです。
ただ、自分としては、妥協したり怠けたりはしませんでした。
一生懸命に取り組んだ結果の今がある、と思っています。
また来年は新たな展開があり、今年の準備がなければそれも無かった。
そう考えれば、また明日を向いて歩いていくしかないんだなぁ、
と思います。
「全ての出来事は、自分に最適なタイミングでやってくる」
私のメンターが授けてくれた言葉。
これを信じて、これからも頑張っていきます。
2. 不動産投資を楽しんだか。
→私の全体の活動の中で、楽しくできたことは半分くらい。
空室が埋まらなかったり、所有物件すべての建物で水漏れが起きたり、予想以上にリフォーム費用がかかったりと、収益には予想以上の打撃を被りました。
それでも保険で助けられたり、被害・出費を最小限に抑えることができて、それはそれで最善の対応ができたと思います。
この一年も、新たな出会いがあり、新たな物件があり、新たな学びがありました。
その中で、特に素敵な人・成功者・前向きな人と結びついたことは、かけがえのない喜びです。
いろいろなブログやFacebookを拝見すると、不動産事業を謳歌している人の多くは
旅行したり、美味しいものを食べているようです。笑
決してそんなことばかりしているわけではないと思いますが、
日頃は地道で弛まぬ努力をしている中、人前では大らかに振舞うことも、
実は成功に近づく要素として大切なんだな、と実感しています。
「来年はもっともっと、旅や食事を楽しもう。」
そんなことを考えました。
3. 来年を、どう過ごすか。
→目標はすでに明確です。
あとはそれを実現するための手段・プロセスをよくよく考えなければなりません。
私は日頃、イベントを実施する業務に携わることがあったり、自らセミナー講師を務めることもありますが、本番をうまく乗り切るには、
「準備が9割」だと思っています。
スピードが速いインターネット業界・不動産業界において、
本当は準備してもし足りないことがないくらいなのですが、
時間は待ってくれません。
「今、できることを今やる」
こうして少しでも効率的に、迅速にやりきることが必要です。
サラリーマンと大きく違うことは
誰も正解を教えてくれないことです。
自分を評価してくれる上司もいないので、
すべては自己責任。
自分の評価は自分で決めるしかありません。
そうしてうまくいかないことも、うまくいくことも
一つ一つ積み上げ
明日への糧にしていくしかなさそうです。
こう考えると、なんだかとても孤独な感じがしますが、
周りを見渡すと、実は味方がたくさんいます。
自分が誠心誠意、他人に尽くしていけば、
いつかその何割かは返ってくる。
そう信じて、今日という日を全力で過ごします。
いつもなら、わき目もふらず
がむしゃらに仕事をし、
傷ついて思い悩むことばかり、
ということもありますが、
こんな日を機会に
ちょっと立ち止まって
明るい希望を持ったマインドセット
を自分に仕掛けるのもいいですね。
そして、このように
実際に文字にしておくことも有効です。
今日も、明日につながる一日を。
*****************
昨日のブログ
不動産投資のプロとアマチュアの違い
*****************
桜木不動産投資塾
のホームページはこちら
関連記事
不動産投資のプロとアマチュアの違い

今朝、何気なくTVを見ていたら、ある情報番組で2014年の詐欺被害の状況について特集が組まれていました。
2014年に全国の警察が把握した振り込め詐欺などの特殊詐欺の被害総額は
約559億4,000万円となり、初めて500億円を超え、過去最悪を更新。
増加は5年連続で、前年と比べて約70億円(14%)増えたそうです。
特殊詐欺の被害総額は全財産犯の現金被害額約1,130億円の49.5%に相当。
そして2015年は、上半期(1月〜6月)で約236億5,233万円。
前年同期よりも約33億円(12%)減少しているものの、
依然として相当な規模に上っています。
最も多い手口としては、
子や孫を装って助けを求める「オレオレ詐欺」が約86億円で7%増加。
次にスマートフォンのサイト利用料などに起因する
「架空請求詐欺」が約85億円で20%増。
最近ではマイナンバー制度を悪用した
寄付金の振込をさせる詐欺なども発生しているそうです。
世の中の広告を見渡せば「オレオレ詐欺に注意」とか「レターパックで現金は送れません」など、さまざまな警告文が目立ち、もはやこんな詐欺に遭う人は減少しているのでは、と思っていましたが、どうやらこの種の詐欺は当分無くならないそうです。
その理由として、今朝の番組のコメンテイターが残した言葉が印象的でした。
詐欺を働く側の人間はプロ。詐欺にかかる側の人間はアマチュア。
アマチュアである一般人は、詐欺被害のニュースを見たり警告を聞いても、
「ああ、大変な目に遭っている人がいるな」、「気をつけなければいけないな」
とその時だけ感じて、
次の瞬間にはもう、忘れているそうです。
ところがプロは、一日中、人を騙すことばかり考え、
防犯活動があればその対策を考え
一年中そのことばかり考えているそうです。
うーん、ちょっとかなり皮肉な例
になってしまいましたが、この
「一日中考え、一年中考え続けるのがプロ」
というセリフは、どんなことにも当てはまることだ
と受け止めました。
不動産投資でも、果たして自分は一日中考えているだろうか
と自問してみます。
プロフェッショナルであり続けること
そのためには一日中、一年中
不動産事業のことを考え続けることが
必要なのです。
物件を購入する時、諦めずに四六時中探し続けることができているか
いろいろな角度、いろいろな情報ソースから探す努力をしているか
を常に意識し続けることが大事なのです。
さらには良い物件を見つけた後は、
仲介不動産会社、管理会社、そして売主さんと話を詰めるとき、
より深く考えている方が話を有利に進められます。
こういう部分を「詰め」と呼んだりしますが、
ただ目の前のチャンスや人に頼るだけで
詰めが甘いと、
肝心な「継続的利益」を失う原因にもなりがちです。
価値ある物件を正しく見つけ、所有後の賃貸経営も着実に遂行する。
そんなプロフェッショナルであり続けたい、
と、年末にあらためて
気を引き締めた一日でした。
*****************
昨日のブログ
2015年 賃貸業界10大ニュース!
*****************
桜木不動産投資塾
のホームページはこちら
関連記事
不動産投資では、物件探しの苦悩が続く

今日は私の不動産物件探しの苦労話を暴露します。
先日、いい加減に自分の要望条件にこだわってばかりいると
この先もずっと物件が買えない状況が続くことを懸念して、
思い切って探し方を変えてみることにしました。
これまでは
返済比率 50%以下
CF(キャッシュフロー)比率 30%以上
になることを基準としていましたが、
これだと利回りが最低でも9%、
そして融資の金利は1%台で
融資期間が25年ないと
ほぼ当てはまらなくなります。
融資期間25年ということは
RC造で築年数が22年以下でなければならず、
この条件で利回り9%、金利1.2%を追い求めていると
もはや時代が変わらない限り
出会うことがなくなってきた感があります。
そこで今度は
「比率」ではなく「キャッシュ」
に着目し、
1億円あたり200万円前後の手残りがあるならば、
他のことには目を瞑ろう
としてみました。
これはどういうことかというと、
残存耐用年数に関係なく
長期間、融資してくれる金融機関があれば
多少金利が高くても
月々の返済金額が少なくなり
毎月の手残りを確保できる
という考え方です。
ここで注意しなければならないのは
資産価値ができるだけ下がらないこと
つまり、土地が広いことなどが求められます。
私のようにオーバーローンを第一としている場合、
長期間融資してくれるからといって、
資産価値が維持できない物件
(例えば建物の現在価値に依存しているような物件)
に手をつけると
年数が経つにつれてたちまち資産価値が下がり、
融資を受けている負債の額の方が大きくなって
資産vs負債のバランスシートが悪化する一方になるからです。
こうなると、なかなか次の銀行の評価が得られなくなり
その先、物件を増やすことが難しくなってしまいます。
その点に注意しながら、
まずは最初の「高すぎる条件」を緩和し
「フルローンを長期で受けられる物件」を探します。
そうして不動産会社にアプローチしてみたところ、
2箇所から同じ内容の
物件情報が届きました。
2社から同じ物件情報が届く、ということは
私の意向が正しく伝わっていることの証でもあります。
それは
築27年のRC 4階建て 駅徒歩2分
融資期間は25年以上とれ、金利は1.5%〜2%前半
利回り8%強
というものです。
久しぶりの検討物件で、
ちょっと前のめりになりました。
少し詳しく見てみると、
・26戸中7室(27%)が空き
→大丈夫。満室にする!
・1Kで家賃はおそらく最低レベル
→よっしゃ、今後収入減の心配なし!
・1部屋、2年前に自然死あり
→そんなの家賃を下げれば問題なし!
と、ここまでは頑張ろうと思ったのですが
・土地面積234㎡
・1部屋の広さ16㎡未満
・バストイレ一緒の3点ユニット
という点が
1.土地が狭く、今後、資産価値を維持できない見込み
2.部屋が狭すぎて客付けに苦労する
(現在の空室率の高さも怖くなってきた)
ということで、今回は見送りました。
実は、ここが思案のしどころで、
現場をしっかりと把握し、必ず満室にする自信があるなら、
この物件を買っても良いかもしれません。
だけど、正直言って
今の私には荷が重い・・・。
満室にできなければ「キャッシュフロー」は相当厳しいものになります。
案内してくれた不動産会社さんには感謝しつつ、
また次の物件を待つことにしました。
もうしばらく、この辺で右往左往してみます。
*******************
昨日のブログ
サラリーマン兼業大家の休日の過ごし方
*****************
桜木不動産投資塾
のホームページはこちら
関連記事
新築アパートを買うならこういう買い方だ!

近頃はめっきり、フルローンが可能なRC物件が少なくなり、厳しい状況を迎えている不動産投資家さんも多いのではないか、と思います。
かくいう私もその一人なのですが、最近はかなりの勢いで「新築アパート」を進める動きが目につくので、固定概念にとらわれずちょっと調べてみることにしました。
ちなみに、新築アパートのメリットやリスクについては
以前にもブログに書いております。
第1話
新築木造アパートがよく売りに出ているけど、気をつけて!
第2話
新築木造アパートを買う時に気をつけたい落とし穴
第3話
不動産投資の失敗談 新築木造アパートの苦難
これらのブログのタイトルからもおわかりのように、
要するに「新築アパート」というのは、あまりお勧めしないわけです。
なぜなら、私が過去に失敗体験をしているからです。
しかし、過去に失敗したからという固定観念を持ち続けていると
やがて時代の波に取り残されるかもしれません。
ですので、新築アパートを勧める人はどんなメリットを提案されているのか、
何冊か本を読んだり、いろいろと調べてわかったことをお伝えします。
新築アパートのリスクといえば、どの本を読んでも、
やはり上記のブログに書いてある通りでした。
ですが、それらのリスクを最小限にするために、
次のような特定の条件のもとで購入せよ、ということなのです。
新築アパートが成功するための条件
- 土地を安く購入し、建物業者は自分で見つけてコストダウンする。
- 場所は東京23区内。しかも駅近。
- 金利1%台の金融機関から融資を受ける。
たしかに、この手法であれば、リスクは極めて低くなります。
ポイントは
・新築はしばらくの間、修繕費がかからない。
・売却時にはオリンピック需要などで価値が上がる確率大。
・利回りと金利のバランスを考えたら、
たとえ利回りが7%台であっても金利1%で融資を受ければキャッシュフローはいい。
少なくとも利回り1で金利4.5%であれば、差し引き5.5%となり、これよりも新築の方が有利、
ということになります。
問題は、どうやってそんな物件を見つけ出すことできるか、ということにかかってきます。
となると、やはり不動産会社にアプローチして、自分が求める物件を探し出してもらうしかないですね。
納得。
但し、ひとつだけ気になるのは、部屋数が少ない物件は空室時のインパクトが特に大きい
ことです。もしも購入する際は、2棟一括など、最初から少しでも規模を多くしておくことが
もうひとつのコツですね。
桜木不動産投資塾
のホームページはこちら
関連記事
これからの不動産投資では、過去の妄想は捨てろ!

最近は不動産投資で王道のRC物件が非常に少なくなっています。
物件自体はたくさん出回っているのですが、正確には
高利回り かつ フルローンが可能な物件
が少ないのです。
数年前、RC(鉄筋コンクリート)物件は
1.利回りが10%〜13%
2.築20年程度のものが多く、
RCの法定耐用年数47年ー20年=27年 となり
残存年数が25年以上
=融資期間が長くとれる
3.土地の価値は多少低くても、RCは建物の価値が高いため
金融機関が物件価格と同額の融資をしてくれる
といった条件が揃い、借入金利がたとえ4.5%と高くても
キャッシュフロー(すべての経費を引いた手取り額)が十分に得られる
こういうケースがメインでした。
しかし最近では
- 利回りは8%台 もしくは7%以下
*利回りとは、「家賃収入」を「物件価格」で割った数値なので
物件価格が高くなれば利回りは低くなる
つまり、物件価格が高騰しているということ
- 築30年以上
築浅のものはさらに物件価格が高く(=利回りが低く)
自己資金の少ない不動産投資家にはとても購入できない
- 金融機関は物件の担保価値を重視
融資をしたがっている金融機関は多い、と聞くけれど、
① 利回りが低い物件については購入者が自己資金で補わないと
収支が成立しない。
② もしくは既に所有している資産を担保にすれば可能性があるが
すでにオーバーローン(物件価格以上の融資)を
借りまくっている人にとっては
それも無理。
ということで、多くの不動産投資家が希望する条件に合う物件は
ますます希少となり、
なかなか昔のように堅実な収益不動産を見つけることが難しくなりました。
今、物件を買えている人は
1)最初の1棟目として、キャッシュフローに目をつぶってフルローンで買う人
余計な負債を抱えていないので、金融機関が融資を出しやすい
2)潤沢な資金があり、利回りが低い分は現金で補填して、
少ない借入でも収支を確保できる人。
さらに数年後に売却すれば、きっと価格が高騰して、売買益が得られることを狙える。
3)既存の不動産や株などを含めた資産があり、
融資の背景として金融機関を安心させる材料を持っている人。
もしくは法人で黒字経営を2、3年継続している人。
こんなケースが多いですね。
そうはいっても、
「物件がない、融資が下りない、買えない」と
うつむいていても何も進みません。
こんな時は、今までの常識にとらわれず、
もう一度収益不動産の戦略を練り直さなければならないのです。
従来はダメと言われていたことが、これからは「あり」かもしれない。
時代の流れに沿って、柔軟な発想が必要な時期に来ています。
桜木不動産投資塾
のホームページはこちら
関連記事
私はなぜ不動産投資をするのか

私は日頃サラリーマンをしていますが、いわゆる「メーカー」に勤務し、商品を企画したり、海外に向けて売れる仕組みを作ったりしています。技術屋ではないので直接開発したり設計したりすることはありませんが、自社の商品の魅力を伝え、販売をサポートする営業活動に従事しています。
しかし、ときどき「これでいいのだろうか」と自分の中で葛藤を覚えることがあります。
会社のモノづくりの考え方・売り方について疑問を感じるからです。
企業というものは、当然ながら利益を追求しなければなりません。
だからこそ商品を生み出すとき
いつまでにいくらの売上を達成するか、の目標を決め、
競合商品を分析し、ターゲットユーザーを定め
相手に勝てるスペック、ユーザーが求めるであろう機能を搭載し、
コスト目標=利益目標を定めて
製造・販売を行っていきます。
社内にいるとこれがとても正しい秩序に思え、疑う余地さえないのですが、一歩外に出て考えると、実はとても違和感を覚えます。
そんな時、ビジネスの本質を捉えた動画に出逢いました。
「サイモン・シネックのゴールデンサークル理論」
動画はこちら。
これはとても有名なTEDのプレゼンテーション動画ですが、
人は「何を」ではなく、「なぜ」に動かされるのだ
ということをとてもわかりやすく解説しています。
スペックや機能が他社より勝っているからといって、
それで「欲しい」と思うユーザーはほとんどいません。
「なぜ」その会社がそのビジネスをしているのか
「なぜ」世の中に必要だと思っているのか
それを伝えることが原点になります。
その観点で、「私はなぜ不動産投資をするのか」と考えると
月収何十万円、何百万円欲しいから
不労所得を得て、自由な時間を過ごしたいから
と言っていては誰にも、何も伝わらないのだな、と思います。
父親として、子供の夢を叶える
家族と幸せな時間を過ごす
そして私と同じ想いを抱く同世代のサラリーマン諸氏に
私の経験とノウハウを伝えて、ともに充実した人生を送りたい
これが心からの願いです。
そのために不動産投資があり
一人でも多くの人と出会う必要があるのです。
物事が思うように進まない時、壁にあたる時、
私はいつも、この原点に立ち返ります。
そしてこの動画を何度も何度も見返して
目標を持つことの意味
伝えることの大切さ
を再認識します。
不動産投資も人と人とのつながりが最重要なので、
一人でも多くの方に自分を理解してもらい、
自分も相手を理解できるようになりたいと思います。
桜木不動産投資塾
のホームページはこちら
関連記事
「老後は1億円必要」という常識?に不動産投資で備える!

今日の日経新聞電子版に、
「老後に1億円必要」は本当か
という記事が掲載されていました。
書かれたのは経済コラムニストの大江英樹さんという方ですが、
結論を言えば、「それは人の考え方によって違う」という、至極ごもっともな本質を、とてもわかりやすく解説されていました。
まず、雑誌などではよく「老後は1億円必要」という特集が組まれるそうです。
このこと自体、私には初耳だったのですが、特集を組んで世間を煽る裏には、金融機関や保険会社の商魂が思い切り見え隠れしているとのこと。
なるほど。ビジネスの広告手法の一つかもしれません。
「老後に1億円かかる」という計算の根拠は、65歳から90歳までの間に、月35万円で25年間生活する、という試算が前提になっているようです。月50万円ぐらいでリッチな生活をしたいのであれば、1億5,000万円かかります。
そこで、サラリーマンの公的年金で、夫婦二人の場合では月の平均的な受給額は約22万円、25年で6,600万円になりますので、プラスαを考えて大体1億円ということだそうです。
仮に1億円としても、7〜8割は公的年金・退職金・企業年金でまかなわれ、あと数千万円を増やす努力をするか、もしくは生活を切り詰めていけば大丈夫。そういう心構えで、あまりメディアの情報に踊らされないよう、自分の頭で考え、自分で判断するように、とのメッセージでした。
確かにその通りですね。何十年も先のことなんて、お金の価値が変わるだろうし、年金制度も不安定、そして自分の健康についてもどうなるかわかるはずがないのですから、人から聞いた話で不安になってばかりいるのは、無駄な時間を過ごすことになります。
そんなことに同感しながら、不動産投資は数十年にわたって安定した収入をもたらす仕組みですから、今のうちに持っておくことが本当に重要なんだなぁ、とつくづく思います。不動産という「資産」を持っていれば、年金への不安や、利殖話にやたらと飛びつく必要もなく、自分の生活をしっかり見つめていくことができると思います。
それでもやはり、不動産投資だって、自分がどうなりたいか、をはっきりさせておかないと、物件選びの際に間違えたり、購入するタイミングを逸したりすることにつながります。
不動産投資家にとっての「老後」があるとしたら、毎月の収入や支出がいくらか、を心配するよりも、得たお金と時間で人生をどう生きるか、を真剣に実践することがより大切だと思うのです。
桜木不動産投資塾
のホームページはこちら
関連記事
不動産投資でいう「利回り」って、いったい何なの?

私は専門用語や業界用語が大キライなのですが、この度、本を出版することになり、できるだけ用語を使わず、トコトンわかりやすく解説し、初めての方でも安心して読みやすい内容にしよう、とコンセプトを決めました。
そして昨日、出版社の方と打ち合わせをした際、編集者さんから
「不動産の利回りって、どのように理解しておけばよいですか」
と念押し確認が入りました。
なるほど。利回りといえば、投資に対するリターンのことですが、
不動産投資でいう「リターン」とはどの部分なのか、
ということがあいまいになることが多いようです。
では、不動産業界で言う「利回り」の意味を3つ、超カンタンに解説します。
1.表面利回り
「グロス利回り」とも言われ、単純に満室時の家賃収入を物件価格で割ったもの。
家賃収入が1,000万円で物件価格が1億円だったら、利回り10%。家賃収入が800万円だったら利回り8%。
つまり、利回りが高いほど、物件価格の割に家賃収入が多い、ということ。逆にいうと、利回りが高い物件は、得られる収益に対して購入価格が安い、となります。
実際には賃貸経営するのに管理費やら税金やらいろいろな経費がかかるので、
家賃収入が1,000万円あったとしても、経費はそこから20%くらい持っていかれます。
表面利回りの通りの収入は、まずあり得ません。
あ、でもこれ、「偽り」とか「騙す」という意図はないのです。あくまでも同じ基準でシンプルに物件を比較するための指標と認識してください。
2.実質利回り
「ネット利回り」とも言われます。
前述の年間家賃収入—20%くらいの経費(管理費や固定資産税など)を計算し
物件を買うときにも登録免許税などの諸経費を上乗せされます。
そういった実質的な投資額と、得られる収入を計算したのが「実質利回り」。
当然ながら、表面利回りよりも厳しい値になります。
管理費や税金は、物件によって大きく変動しますから、いざ買おう、と思った際に、慎重に検討するべきものです。
ところでこの「グロス利回り」とか「ネット利回り」とか、時々本に書いてあったりするので記載してみましたが、はっきり言って覚える必要ありません。
カタカナを使えばいいってもんじゃない。
表面利回り・実質利回り で十分意味が通じます。わざわざわかり難くすることもないのです。
「本質はココ!」
表面利回りの高い物件を見て飛びついても、
それはほとんどが空室だったり、
老朽化していて修繕費がかかったり、
エレベーターや立体式駐車場があって電気代などの経費
が大きくかかってしまうような物件であることが多いのです。
表面利回りが高いものは高いなりの理由がある、ということです。
それでも、基準はみな「表面利回り」で表示されています。
表面利回りの高さだけに魅力を感じていると火傷するので、
まず「表面利回り」を基準にして物件をふるいにかけ、
気になる物件を見つけたら個別に「実質利回り」を確認する、
という順序でアプローチするのです。
3.NOI利回り
あともう一つ、業界ではNOIといって、経済評論家が好きそうな利回りがあります。
これは Net Operating Income の略で、
覚えておくと
へぇー、よく知っているねー。と言われることがあります。
でもそれだけです。
会社の経営状況をどこかで発表するときには、このNOI、つまり
営業純利益とは、
満室賃料前提のオメデタイ数字は使いません。
収入には実際に空室だった期間の家賃をカウントせず、
運営にかかるさまざまな経費を全部差し引いたものを「営業純利益」と呼び、
不動産価格で割ったものを「NOI利回り」といいます。
NOIは実際に経営して初めて論じられるものですので
買う前に出ているものがあるとしたら、それはあくまでも予測、ということで
気にしなくて良いと思います。
とにかく一般的に不動産投資でいう「利回り」とは
「表面利回り」のことで、
物件を比較するときにはある程度参考になるけれど、
購入するときには、
借り入れ金利や管理費・経費を同時に考えて
いくらくらいお金が手元に残るのか
ということを意識しておくことの方が
よほど重要なのです。
桜木不動産投資塾
のホームページはこちら
関連記事
不動産投資家が心得る、お金のつかい方とは?

不動産投資をしていると、ビジネスで成功して裕福な状態を築いた人と知り合いになる機会が多く、お金の価値観もなんだか私の感覚とは一桁違うような感じで戸惑うことがあります。
そんな成功者の方々とご一緒しているうちに「3通りのお金のつかい方」について学びましたのでご紹介します。
お金の遣い方は、消費・浪費・投資の3つに分けられます。
1.消費
生活に必要なことにお金を使うこと。ないと生活できないものを買う。生きていくために必要な出費。
2.浪費
無くても困らないもの、何も生み出さないものを買うこと。いわゆる無駄遣い。
3.投資
やがて利益をもたらすものにお金を遣うこと。不動産を買うことはもちろん「投資」の一つ。
ここで着目したいのは、「投資」とは、必ずしも直接お金を出すことだけを指すのではない、ということです。
その一つは「時間への投資」。
例えば雨の中駅まで歩き、電車をいくつも乗り換えて移動するのではなく、タクシーに乗ることがあります。
こうすることで、車の中で電話をしたり、メールをチェックするなど、時間を有効に使えます。その行為によってお金を生み出すことができるなら、それはれっきとした投資です。
2つ目は「自分への投資」。
これは既に自己投資と言われ確立されていますが、セミナーを受けたり、教材を購入したりすることもその一つ。
そしてさらに、ファッションに気を使ったり、品質の高いものを身に付けることによって自分のブランドを向上させることだって、十分「投資」と言えるのです。
自分の外観・身の回りの品位を高めることによって、同類の人々と会話するチャンスも生まれます。
3つ目は「空間への投資」。
例えば美味しい料理を、上質な雰囲気のお店で味わうこと。こうすることによって、お店の人のプロフェッショナルなおもてなしに触れ、会話や仕草の中に学びを得ます。
新幹線のグリーン車や飛行機のビジネスクラスの利用も同様に、約束されたゆとりの空間を過ごすことで、リラックスして睡眠をとったり、仕事に集中したりと、次にお金を生み出すための準備を整えることができます。
他にも様々な投資のスタイルがありますが、要は考え方・活かし方ひとつで変わってくるのです。
一見、無駄遣いに思えても、自分がしっかりと未来に活かすことができることを「投資」と呼び、逆に勉強したり研究に時間を費やすことがあったとしても、何も生み出すことがなければ「浪費」となってしまうのです。
不動産投資は「投資」と名付けられていますが、だからこそ、必ず利益を生み出さなければならないし、そういう考えをしっかり持って取り組むことが大切です。
頭金ゼロで7億の資産をつくる
桜木不動産投資塾
のホームページはこちら
関連記事
不動産オーナーになると法定点検が義務づけられます

最近、マンションの基礎工事の不備による訴訟が取り沙汰され、日本中のマンションに住む人々は少なからず「自分のところはどうなんだろう」と不安な気持ちになっていると思います。
一方、収益不動産を持つオーナーも、「自分のマンションは大丈夫か」と心配がよぎります。
新築でさえ、手抜き工事をされているかもしれないのに、中古で購入したものなら
なおさら確認することは難しいし、築何十年なんて、もはや最初に建築したところも販売した会社も無くなっていることさえあり得ます。
そもそも私たちが物件を購入するとき、そこまでしっかりと建築構造を確認できるでしょうか。
価格・利回り・立地・築年数・間取り等に着目することはあっても、なかなか内部までは調べられないし、設計図面など見てもチンプンカンプンです。
せめて修繕履歴を確認することがせいぜいですが、それでも書いてある項目をきちんと理解しているかというと、そうでもありません。
そんなオーナーが、これからの対策としてできること、
それが「法定点検」です。
これには多少の費用がかかりますが、
「経費節減のため法定点検はやらない」
という選択肢はないと思います。
人間の健康診断と同じですので、何かが起きてからでは遅いのです。
共同住宅では、建築基準法、消防法等の法律に定められた定期検査を実施することが義務付けられています。
主な点検項目としては下記が挙げられます。
1.消防設備点検
機器点検は年2回、総合点検は年1回。
消防設備とは、「消火設備」「警報装置」「避難設備」「消防防水」「消火活動上必要な設備」に大きく分類され、きちんと使えることを、管轄の消防署長へ報告しなければなりません。
2.貯水槽の点検
年1回の清掃。飲料水になるので衛生的に維持する責任があります。水道法・ビル管理法により水質の定期点検が義務付けられています。
3.エレベーター保守点検
法定点検は年1回と義務付けられていますが、エレベーターが止まる、ということは住民に与えるインパクトが非常に大きいため、メンテナンス業者と契約して毎月点検することをお勧めします。
私のマンションでも、先々月、急にエレベーターがストップしてしまい、メンテナンス会社に即対応してもらって事なきを得た、ということがありました。原因は基盤の劣化による故障ということで、補修に7万円かかりました。
エレベーターがあると、けっこう維持費がかかります。もしも総交換が必要になると、何百万円、あるいは1千数百万円かかるケースもあります。
ですので、エレベーターが必要ない、3階〜4階建てで、横に広いマンションは、投資家にとって非常に魅力的に見えるのです。
このほか、建物の規模や営業形態によって追加される項目がありますが、ここでは割愛します。
「点検」というのは、「今、異常がないからいいや」と後回しにしてしまいがちですが、万が一の被害を最小限に抑えるためにも、必ずやっておくべきことです。長い目でみればリスク回避につながる重要な項目の一つです。
これから不動産を所有する人、所有したばかりの人は、通常の管理費のほかに、こういう経費もかかるんだ、と認識しておいた方がよいと思います。
そして、この点検は主に専門の資格を持った人しかできないものが多いので、できるだけ管理会社に任せることをお勧めします。
何もトラブルが起きないことが一番。でも万が一の備えは、経営者としても必須の対策です。
頭金ゼロで7億の資産をつくる
桜木不動産投資塾
のホームページはこちら
関連記事
コンテナ(貸し倉庫)ビジネスは不動産投資といえるのか?

先日、懇意にしていただいている地銀の支店長から直々に電話があり、投資案件を進められました。
普通は私の方から融資してもらいたい物件を銀行に持ち込んで検討してもらうのですが、最近は持ち込む物件が今イチ収益性に物足りず、ことごとく却下されていることもあり、支店長の方から「こんなのはどうですか」と提案をいただいた次第です。
金融商品でもない案件をわざわざ支店長から案内していただくなんて、これまでになかったことですし、銀行の支店長が勧めるのだから絶対安全・お得な情報なのだろうと、前のめりになって話を聞きました。実際、すでに5、6件申し込みがある、とのこと。
支店長から案内された案件は、コンテナへの投資で、年利回り11%、10年契約というものです。一口1,000万円の現金払い。そうすると10年間にわたり、毎年110万円ずつがフトコロに入って来て、契約満了後にはコンテナの会社が同価で買い取ってくれる、という感じです。
年利11%の定期預金のようなものですね。
さらにこの商品は翌年に「減価償却費」をごっそり(購入金額の6〜7割程度)計上できるので、利益が大きい法人においては節税対策にもなります。
ちなみにここで言う「コンテナ」とは、いわゆる「レンタルボックス」とか「トランクルーム」と言われるもので、事務所や家の収納が足りない人が、外部に借りる保管スペースのことです。
私の家の近所にも、JRの高架下にトランクルームがあり、常に満室の状況のようです。
最近の収益不動産は、実質利回り11%なんてまずあり得ません。しかもコンテナは管理費もほとんどかからず、ほぼ満室状態を保てるほど需要がありますので、考え方によっては太陽光設備よりも確実な収益が得られるかもしれません。
支店長からはそのように説明がありました。
私は電話を受けた段階からほとんど”購入しよう”という気持ちでしたが、話を聞いているうちにすぐにクールダウンしていきました。
その理由は、「トランクルームでは融資がつかない」ということです。
融資がつかないのは、担保価値がないからですね。
では銀行のメリットは?と尋ねると、
「コンテナを運営する会社から、仲介手数料として3%が銀行に入る」
とのことです。
融資ができない、担保価値がない、ということは、
もしもこの「コンテナ」を契約してしまった場合、
今後私が不動産物件を買い進めようとする際、
・資産として認められない
ということを意味します。
そんなものに投資するなら、現金をキープしておいて次の融資の時に「資産」として見せる方がよほど効果的です。
この私の考え方を説明し、丁重にお断りすると、
支店長も「おっしゃる通りですね。」と納得されました。
さらに
「私はお金を”投資”して増やしたいのではなく、事業家として”経営”をしたいのです。
資産にならないことにお金を遣いたくありません。」
といって、この機会に私のスタンスを明確に印象づけておきました。もちろん次の融資につなげるためです。
私の場合、キャッシュがあるからといって、今はやみくもに高利回り商品に手を出す段階ではありません。もう少し資産を増やし、万全な体制を築いておくことが先決です。
新しい情報・案件を手に入れることに魅力も感じたのですが、このように明確なポリシーを持っていると、安易な儲け話に乗っかることなく、相手にもきちんと理解してもらえる、ということを学びました。
頭金ゼロで7億の資産をつくる
桜木不動産投資塾
のホームページはこちら
関連記事
新築木造アパートがよく売りに出ているけど、気をつけて!

最近は利回りの高いRC(鉄筋コンクリート造)のものがなかなか売りに出されず、大体7%台、よくても8%台になって来ています。たまに9%台があっても、築30年以上などのかなり古いものばかり、という市場状況です。
そんな中、不動産仲介業の会社からメルマガ等で案内されるものに、新築木造アパートが目立つようになってきました。利回りは8%から9%ですが、新築であれば当分の間、修繕費もかからず、何より客付けに対して「新築」という強いブランド力を発揮できます。
そして需要の多いエリアの新築であれば、金融機関もまだまだフルローン、オーバーローンを出してくれる可能性が高いため、不動産会社としても売りやすい物件としてランクインしてくるのだと思います。
一方、私は昨年、2棟の木造アパートを売却し、現在はRCを3棟所有していて、今なお買い増していこうと日々努力していますが、融資を引けるほど充分な収益を上げられるRC物件にはなかなか出逢えないので、つい「新築木造でもいいか」と思いがちです。
そんな自分へ自戒の念を込めて、自らの経験から新築木造アパートのリスクについてお話ししておこうと思います。
1.資産価値が急激に下がる可能性がある。
新築物件は大抵、売り出す時に広告費をかけられていますので、その分価格に上乗せされているものが多いです。つまり、純粋な資産価値+αで売価設定されているので、購入後の資産としてはその分、目減りします。
フルローンやオーバーローンで融資を受けた場合には、当分の間、資産よりも残債の方が上回りますので、その分、負債を抱えていることになります。
こうなると次に収益物件を購入する際、金融機関から「負債の多い人」と見なされ、なかなか融資を受けられなくなってしまいます。
2.購入時の家賃はほぼ維持できない。
購入するときは「新築」なので、家賃設定も高く、売価が高くてもそれなりの収益が見込まれるため、必然的に利回りが高く見えます。しかしながら、最初の入居者が一旦退去してしまうと、次に募集するときは「新築」とうたえないため、家賃を維持するのが難しくなってきます。
そのアパートに希少価値があり、家賃を下げなくても人気が高い場合には大丈夫かもしれませんが、もしも周辺に同じようなアパートが後から建ってくると、その新築の方が安い家賃に設定されたりして、結果的に市場全体の家賃が下がってしまう恐れもあります。
3.空室が出たときのインパクトが大きい。
これはアパートというよりも規模の問題で、8%〜9%程度の物件で、部屋数が6室〜10室程度の規模だと、1部屋空いたときにキャッシュフローに与えるインパクトが大きくなります。
例えば1部屋6万円の部屋が6室あると月36万円の収入がありますが、1部屋空いてしまうとその分の家賃収入(6万円)が無くなる上、クリーニング費用(約2万円)と新規募集の広告費(約6万円)と合わせておよそ14万円が飛んでいきます。つまり、いきなり約4割程度の収入減となってしまいます。
すぐにまた空室が埋まればよいのですが、これが2ヶ月、3ヶ月と決まらない場合には、さらに毎月6万円ずつが予算から無くなっていき、胃の痛む思いをしなければなりません。
しかしながら、デメリットやリスクばかりに目を向けて、不安だけを煽っても仕方ありませんし、それではどんな物件も買えなくなってしまいます。
不動産投資は何より「目的」が大事ですので、短期間にどんどん物件を増やしていくつもりがなく、じっくりとアパート経営を行って少しずつでも着実な収益を得たい、という目的の場合には、新築アパートも良いかもしれません。
最近は10年間家賃変更なしのサブリース(満室前提での一括借り上げ)を提唱する不動産会社もありますので、そうすれば上記のリスクもある程度回避できます。
絶対にこの物件を買ってはいけない、などというものは存在しません。自分が投資家として何を目指しているのかを日々意識し、市場環境の変化に柔軟に対応していく心構えも大切です。
頭金ゼロで7億の資産をつくる
桜木不動産投資塾
のホームページはこちら
関連記事